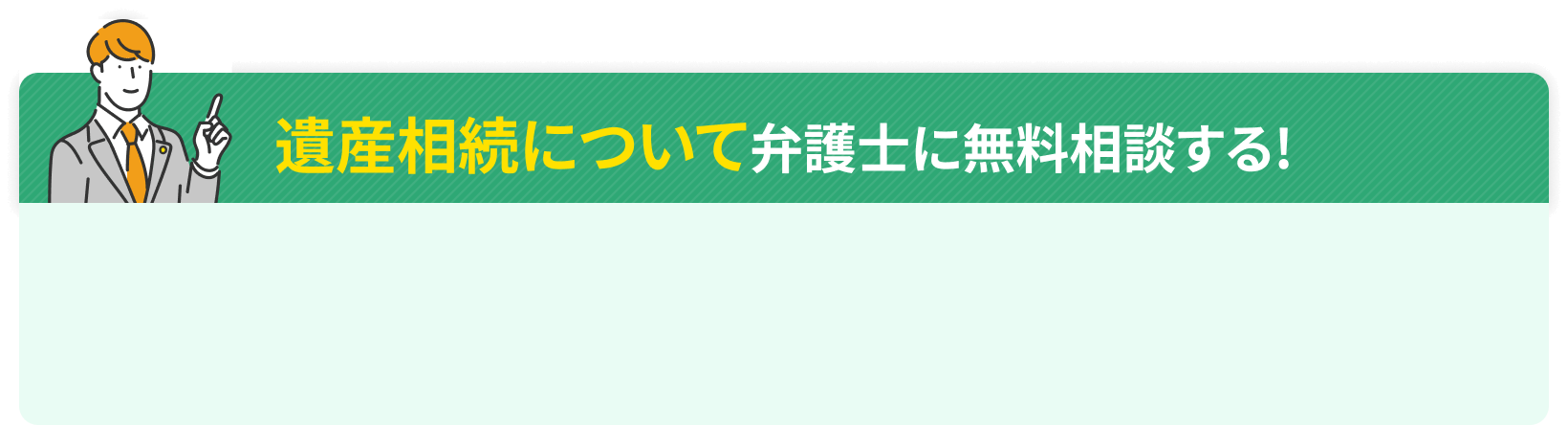相続放棄するためには相続放棄申述書を作成する必要がありますが、書き方にはルールがあります。
相続放棄には期限が定められているため、ミスなく迅速に対応しなければいけません。
また、相続放棄では相続放棄申述書以外の書類も必要で、「誰が相続放棄するのか」によって必要書類が異なります。
手続きを失敗しないためにも、相続放棄申述書の入手方法や作成方法だけでなく、相続放棄申述書以外に必要な書類についても知っておきましょう。
本記事では、相続放棄申述書の入手方法・作成方法・提出方法や、相続放棄するために知っておくべきポイントなどを解説します。
相続放棄を考えている人は参考にしてください。
相続放棄の手続きに不安がある方へ
相続放棄したくても申述書の書き方がわからず、今後の手続きに不安を感じていませんか?
結論からいうと、相続放棄の手続きで悩んでいるなら弁護士へ相談することをおすすめします。
相続放棄には3ヵ月の期限があり、期限内に手続きできないと単純承認とみなされてプラスの財産もマイナスの財産も相続することになってしまいます。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。
- 相続放棄の手続きの方法や流れがわかる
- 本当に相続放棄すべきか判断できる
- 代理人として相続放棄の手続きをスムーズに進めてくれる
- 相続人全員が相続放棄した場合の対応も相談できる
当サイトでは、相続放棄を得意とする弁護士をお住まいの地域から探すことができます。
無料相談はもちろん、電話相談やオンライン相談に対応している法律事務所も多数掲載しているので、まずは気軽に相談ください。
相続放棄申述書とは?
相続放棄申述書とは、相続放棄する際に家庭裁判所に提出しなければならない書類のことです。
被相続人(亡くなった人)が多額の借金を抱えていた場合など、相続をしたくないときには、相続放棄を考えることになります。
ただし、裁判所はあくまでも中立的な立場にあるため、法律に則って債権者側の権利についても保護しなければいけません。
相続放棄を認めてもらうためには、相続放棄申述書などの書類を準備して、相続放棄の妥当性を主張することになります。
相続放棄が認められれば、たとえ被相続人の借金が数千万円におよぶ場合でも返済義務を免れることができます。
相続放棄申述書の入手方法【ダウンロード可】
相続放棄申述書は家庭裁判所の窓口で入手できます。
各家庭裁判所の場所は「各地の裁判所|裁判所」を確認してください。
相続放棄申述書は裁判所ホームページからダウンロードすることもできます。
詳しくは以下のリンクを確認してください。
相続放棄申述書の書き方・記入例
相続放棄申述書は複雑な書式ではありませんが、ダウンロード様式は片面印刷、住所は戸籍謄本と同一にするなどの細かなルールもあります。
相続放棄申述書は成人用と未成年者用の2種類あり、申述人が成人の場合の記入例は以下のとおりです。


引用元:相続の放棄の申述書(成人)|裁判所
一方、申述人が未成年者の場合の記入例は以下のとおりです。


引用元:相続の放棄の申述書(未成年者)|裁判所
ここでは、相続放棄申述書の書き方について解説します。
パソコンや代筆でも作成可能
相続放棄申述書は、手書きだけでなくパソコンで作成することも可能です。
なお、代筆でも作成可能ですが、代筆の場合は家庭裁判所から電話などで確認されたり、委任状の提出を求められたりすることがあります。
1.申述先の家庭裁判所名や年月日を記入して署名押印する
「申述先」には相続放棄を申し出る家庭裁判所の名前を記入します。
たとえば、東京家庭裁判所であれば「東京」と記入してください。
なお、記入する裁判所名は、通常亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
年月日については、相続放棄を申し出る日付を記載しましょう。
2.申述人の情報を記入する
「申述人」には、本籍・住所・電話番号・氏名・生年月日・職業・被相続人との関係などを記入します。
3.法定代理人等の情報を記入する(申述人が未成年の場合)
未成年者が相続放棄する場合は、「法定代理人等」の記入が必要です。
親権者または後見人の住所・電話番号・氏名などを記入しましょう。
電話番号については、平日の日中に連絡のつく番号を記入することが大切です。
4.被相続人の情報を記入する
「被相続人」には、本籍・最後の住所・氏名・死亡日・死亡当時の職業などを記入します。
本籍については戸籍謄本、最後の住所については住民票の除票を取り寄せて確認しましょう。
なお、本籍と最後の住所が申述人と同じであれば、「申述人の本籍・住所に同じ」と記入して構いません。
5.申述の趣旨を記入する
「申述の趣旨」には、あらかじめ「相続の放棄をする」と印字されているので、何も記入する必要はありません。
6.申述の理由と相続の開始を知った日を記入する
「申述の理由」には相続の開始を知った日を記入しますが、その際は間違いがないように注意しましょう。
相続の開始を知った日とは、「自分が相続人になったことを知った日」のことを指します。
相続時の状況によって変わるものの、基本的には「被相続人の死亡日」になることが多いでしょう。
相続放棄では「相続の開始を知った日から3ヵ月以内」に手続きを済ませなければならないため、正確な起算日を把握しておくことが大切です。
もし期限を過ぎてしまっても、対応が遅れた理由などを記載した「上申書」を添付することで認めてもらえることもあります。
ただし、その際は期限内の申述が不可能であったことの正当性を証明しなければいけません。
すでに期限を過ぎてしまっている場合は、相続分野に注力する弁護士にサポートしてもらうことをおすすめします。
7.放棄の理由を選択する
「放棄の理由」では該当する項目に丸をつけるだけですが、もし該当するものがなければ「その他」を選択し、理由を簡潔に記入しましょう。
基本的に、ここでの記入内容は相続放棄の受理・不受理に影響しませんので、「相続に関わりたくないから」「母親に財産を多くもらってほしいから」などと正直に書いてください。
8.相続財産の概略を記入する
「相続財産の概略」には被相続人の資産や負債などの内訳を記入します。
不動産の坪数や預貯金の金額など、内容は分かる範囲のもので構いません。
もし判明していない財産がある場合は、空欄にするか、「不明」と記入しましょう。
9.収入印紙を貼付する
相続放棄申述書には、800円分の収入印紙の貼付が必要です。
収入印紙は、郵便局・裁判所・コンビニエンスストアなどで購入しましょう。
【ケース別】相続放棄の申述に必要な書類
相続放棄では、相続放棄申述書だけでなく、以下のような書類も必要です。
相続放棄の必要書類
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人の戸籍謄本
- 収入印紙(800円)
- 切手(82円を5枚程度)
なお、被相続人との関係性によっては上記以外の書類が必要になるケースもあり、以下ではケースごとの必要書類について解説します。
被相続人の配偶者・子どもが相続放棄する場合
被相続人の配偶者や子どもが相続放棄する場合は、以下の戸籍謄本を準備します。
被相続人の死亡については、死亡届の提出後3日~5日程度で戸籍謄本に記載されるため、相続開始直後に取得しないよう注意してください。
被相続人の孫が相続放棄する場合
被相続人よりも先に被相続人の子どもが亡くなっている場合には、孫が相続人となります。
これを代襲相続といい、相続放棄する場合は以下の戸籍謄本を準備します。
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
- 被代襲者(被相続人の子ども)の死亡の記載のある戸籍謄本
被相続人の父母や祖父母が相続放棄する場合
被相続人の子どもや孫が亡くなっている場合や相続放棄している場合には、父母が相続人となります。
なお、すでに父母が亡くなっており祖父母が存命中の場合は、祖父母が相続人となります。
被相続人の父母や祖父母が相続放棄する場合、以下の戸籍謄本を準備します。
- 被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本
- 被相続人の子ども・孫の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本(子ども・孫が亡くなっている場合のみ)
- 被相続人の父母の死亡の記載のある戸籍謄本(祖父母が相続放棄する場合のみ)
被相続人の兄弟姉妹または甥・姪が相続放棄する場合
被相続人の子ども・孫・親・祖父母が亡くなっている場合や相続放棄している場合には、兄弟姉妹が相続人となります。
なお、すでに兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥・姪が相続人となります。
被相続人の兄弟姉妹や甥・姪が相続放棄する場合、以下の戸籍謄本を準備します。
- 被相続人の子ども・孫の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本(子ども・孫が亡くなっている場合のみ)
- 被相続人の父母や祖父母の死亡の記載のある戸籍謄本(父母や祖父母が亡くなっている場合)
- 兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍謄本(甥・姪が相続放棄する場合)
戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役場で入手できます。
ただし、ケースによってはいくつもの役所を回らなければならず、収集途中で相続放棄の期限を迎えてしまう恐れもあります。
どこまで自分でできるのかを見極めて、無理を感じたら速やかに弁護士に依頼することをおすすめします。
なお、相続放棄の必要書類については、「相続放棄の必要書類すべて|ケース別の一覧表と提出方法を解説」で詳しく解説しています。
相続放棄の申述にかかる費用
相続放棄の申述手続きでは、以下の費用がかかります。
郵便切手代については裁判所によって異なるため、詳しくは直接確認しましょう。
- 相続放棄の申述手続き費用
- 収入印紙代:800円
- 連絡用の郵便切手代:400円程度
相続放棄申述書を提出したあとの流れ
相続放棄申述書を提出したあとは、家庭裁判所にて審理が開始されます。
期限内に提出できたからといって、すぐに相続放棄が認められるわけではありません。
ここでは、書類提出後の流れについて解説します。
1.相続放棄の照会書・回答書に回答を記入して返送する
相続放棄の申述から約1週間~2週間後、家庭裁判所から照会書・回答書が送付されます。
書類には以下のような事項が記載されており、回答を記入して返送しましょう。
- 相続放棄する意思は変わらないか?
- 被相続人が死亡したことを知った日はいつか?
- 相続放棄することの意味や、相続を受ける権利がなくなることを知っているか? など
照会書・回答書の様式は各裁判所によってまちまちで、もし書き方がわからない場合は弁護士に相談しましょう。
返送が遅れると、そのぶん相続放棄が完了するまでの日数も延びるため、なるべく早めに対応してください。
2.相続放棄申述受理通知書が送付される
返送後、特に問題がなければ相続放棄申述受理通知書が送付されます。
相続放棄申述受理通知書とは、「相続放棄申述書を受領しました」という内容の書類で、受領すれば相続放棄の手続きは終了となります。
なお、裁判所で扱われる事案は全て事件として表記されるため、相続放棄申述受理通知書には事件番号が記載されています。
これは取扱番号や受付番号のようなものなので、特に気にする必要はありません。
3.必要に応じて相続放棄受理証明書を取得する
相続放棄申述受理通知書は、あくまでも申述人への通知用書類であり、第三者向けの書類ではありません。
債権者によっては、相続放棄申述受理通知書を提示して相続放棄したことを伝えても納得してくれないこともあります。
もし債権者が証明書を要求してきた場合には、家庭裁判所にて「相続放棄申述受理証明書」を取得し、提出しましょう。
なお、相続放棄申述受理証明書の発行を申請する際は、以下の書類や費用が必要です。
申請書については相続放棄申述受理通知書の中に同封されていますが、「相続放棄申述受理証明書|裁判所」からダウンロードすることもできます。
相続放棄申述受理証明書の発行に必要な書類と費用
- 申請書
- 発行手数料(150円分の収入印紙)
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 法定代理人の本人確認書類(申述人が未成年者の場合)
- 返信用封筒と返信用切手(郵送で申請する場合)
- 相続放棄申述受理通知書
相続放棄申述受理証明書は、相続放棄の申述人以外でも申請できます。
たとえば「自分より先順位の相続人と連絡が取れない」「折り合いが悪くて相続放棄したかどうか直接聞けない」というような場合は、相続放棄申述受理証明書を取得することで、相続放棄したかどうかを確認できます。
相続放棄の申述人以外が申請する際は、以下の書類を用意しましょう。
申述人以外が相続放棄申述受理証明書を発行する際に必要な書類・費用
- 申請書
- 発行手数料(150円分の収入印紙)
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 被相続人の住民票除票(本籍地がわかるもの)
- 照会者と被相続人の戸籍謄本(照会者と被相続人との関係がわかるもの)
- 照会者の住民票(本籍地がわかるもの)
- 相続関係図(手書きでも可能)
- 委任状(弁護士に依頼している場合)
- 返信用封筒と返信用切手(郵送で申請する場合)
相続放棄を弁護士に依頼したほうがよいケース
弁護士には、相続放棄の申述を依頼できます。
相続放棄申述書の記入を代行するだけでなく、代理人として手続きをしてくれるので、不備なくスムーズに相続放棄することができます。
特に、以下のようなケースでは依頼するメリットが大きいため、該当する人は早めに弁護士に相談しましょう。
債権者から厳しい督促を受けている場合
被相続人の借金を理由に相続放棄する場合、手続きが完了するまでの間に債権者から返済を迫られることもあります。
特に複数の債権者がいる場合は、督促に対応するだけでもかなりのストレスになるでしょう。
相続放棄と債権者対応を弁護士に依頼すると、債権者には「本人の代わりに弁護士が手続きに対応する」ということを記載した「受任通知」という書類が送付されます。
受任通知が送付されると、電話などによる督促はストップします(賃金業法第21条1項9号)。
弁護士のほかに司法書士も受任通知を送付できますが、「司法書士が対応できるのは1社あたりの債権額が140万円までのケースのみ」という制限があり、債権者対応には限界があります。
厳しい督促は家族にとっても負担になるので、早めに弁護士へ相談してストレスから解放されましょう。
相続放棄するための時間を確保できない場合
相続放棄のために役所や裁判所とやり取りする場合、基本的には平日の昼間に対応することになります。
場合によっては、財産調査などのために銀行・証券会社・法務局ともやり取りしなければならないこともあります。
重要な仕事の予定が入っていて休むことができない人もいれば、健康上の理由からすぐには対応できない人などもいるでしょう。
弁護士には手続きの大部分を依頼でき、相続放棄申述書の作成だけでなく、書類収集・財産調査・家庭裁判所への申述なども代理してくれます。
相続放棄するための時間を確保できない場合は、なるべく早めに弁護士へ相談してください。
相続放棄を弁護士に依頼する場合の費用相場
相続放棄を弁護士に依頼する場合、費用は5万円以上かかるのが一般的です。
自分で手続きする場合に比べると高く感じるかもしれませんが、そのぶん十分なメリットが望めます。
手間と時間や相続放棄の失敗リスクなど、総合的に考えて判断しましょう。
弁護士費用の内訳・相場
- 相談料:0円〜1万円程度/60分
- 相続放棄申述書の作成代理費用:5,000円〜1万円程度(戸籍謄本の取得・実費含む)
- 代理手数料:5万円~10万円程度
なお、上記はあくまで目安であり、法律事務所によって費用は異なります。
詳しい内容は相談時に確認できますが、ホームページで料金体系を公開している弁護士も多いです。
また、料金体系だけでなく、各弁護士の解決実績や注力分野などが掲載されていることも多いので、まずはインターネットで情報収集するのがよいでしょう。
相続放棄を弁護士に依頼する際の選び方や、弁護士費用などについて詳しく知りたい人は、以下の記事も参考にしてください。
相続放棄申述書の作成を弁護士に依頼したほうがよいケース
弁護士には、相続放棄の申述を依頼できます。
相続放棄申述書の記入代行だけでなく、代理人として手続きを進めてくれるので、不備なくスムーズに相続放棄することができます。
特に、以下のようなケースでは依頼するメリットが大きいため、該当する人は早めに弁護士に相談しましょう。
相続放棄の期限が迫っている場合
相続放棄するためには期限内に手続きを済ませる必要がありますが、役所や裁判所とやり取りする場合、基本的には平日の昼間に対応することになります。
場合によっては、財産調査などのために銀行・証券会社・法務局ともやり取りしなければならないこともあります。
なかには重要な仕事の予定が入っていて十分な時間を確保できない人もいれば、健康上の理由からすぐには対応できない人などもいるでしょう。
弁護士なら手続きの大部分を依頼でき、相続放棄申述書の作成だけでなく、書類収集・財産調査・家庭裁判所への申述なども代理してくれます。
期限内に手続きを済ませられるか不安な場合は、なるべく早めに弁護士へ相談してください。
被相続人の財産状況がわからない場合
なかには「被相続人の財産調査が難航していて、どれだけ資産や借金があるのかわからない」ということもあるでしょう。
このようなケースで安易に相続放棄を選択してしまうと、マイナスの財産よりプラスの財産のほうが多く残っていても一切受け取れず、結果的に損を被ることになる可能性があります。
相続では、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も引き継ぐ「限定承認」などの相続方法もあり、状況によって最適な選択肢は異なります。
弁護士なら被相続人の財産調査を依頼することもでき、調査結果をもとに相続放棄するべきかどうかアドバイスしてもらうこともできます。
相続方法の選択を誤って損をすることがないよう、被相続人の財産状況がわからない場合も弁護士に相談しましょう。
債権者から厳しい督促を受けている場合
被相続人の借金を理由に相続放棄する場合、手続きが完了するまでの間に債権者から返済を迫られることもあります。
特に複数の債権者がいる場合は、督促に対応するだけでもかなりのストレスになるでしょう。
相続放棄と債権者対応を弁護士に依頼すると、債権者には「本人の代わりに弁護士が手続きに対応する」ということを記載した「受任通知」という書類が送付されます。
受任通知が送付されると、電話などによる督促はストップします(賃金業法第21条1項9号)。
弁護士のほかに司法書士も受任通知を送付できますが、「司法書士が対応できるのは1社あたりの債権額が140万円までのケースのみ」という制限があり、債権者対応には限界があります。
厳しい督促は家族にとっても負担になるので、早めに弁護士へ相談してストレスから解放されましょう。
相続放棄申述書に関するよくある質問
ここでは、相続放棄申述書に関するよくある質問を解説します。
相続放棄申述書に書き間違いがあったらどうなる?訂正方法は?
提出した相続放棄申述書に書き間違いがあると、家庭裁判所から訂正を求められる可能性があります。
家庭裁判所から連絡が来た際は速やかに対応しましょう。
相続放棄申述書の作成中に書き間違いに気付いた場合は、間違えた部分に二重線を引いて訂正印を押し、脇に書き直してください。
相続放棄申述書は代筆でもよい?
相続放棄申述書は代筆可能です。
相続放棄では「誰が書いたのか」よりも「本人の意思によるものかどうか」が重要視されます。
原則としては本人による自署ですが、代理人に一任した場合は、代理人の記名押印だけでも受理されます。
基本的には代理人(代筆者)への委任状なども不要ですが、もし家庭裁判所から指示があった場合は作成しましょう。
場合によっては、裁判所から電話で意思確認されることもあります。
相続放棄する人の判断能力が低下している場合はどうすればよい?
認知症などで申述人の判断能力が著しく低下している場合は、相続放棄の申述が認められません。
そのようなケースでは、法定後見制度を利用し、成年後見人が代理するという方法があります。
法定後見制度とは、判断能力が不十分な人について、家庭裁判所によって選任された成年後見人がサポートするという制度のことです。
ただし、成年後見人の選任にあたっては家庭裁判所への申し立てが必要であり、一般的には3ヵ月以上の期間を要します。
したがって、相続放棄の期限に間に合わない可能性が極めて高いため、期限経過後の申述も想定しておかなければいけません。
家族の協力だけでは限界がありますので、弁護士に相談したほうがよいでしょう。
相続放棄の照会書は再発行してもらえる?
照会書を紛失しても再発行は可能です。
ただし、受け取りは郵送になるため、郵便切手や封筒などを準備する必要があります。
また、最短で対応しても2日~3日程度はかかることになるため、なるべく早めに返送しましょう。
相続放棄の照会書の送付先を変更したい場合はどうすればよい?
何らかの事情で照会書の送付先を変更することになった場合は、「送達場所等の届出書」という用紙を裁判所に提出すれば、指定の送付先に変更してもらえます。
たとえば、「相続放棄申述後に長期出張となり、ホテルへ照会書を送ってもらいたいケース」や「入院したため病院に送ってもらいたいケース」などがあるでしょう。
「送達場所等の届出書」は、家庭裁判所の窓口や各裁判所ホームページでダウンロードできます。
さいごに|相続放棄申述書の作成が不安な場合は弁護士に相談を
相続放棄申述書は、裁判所ホームページの記入例などを参考にすれば自力でも作成できます。
ただし、相続放棄するためには「相続の開始を知った日から3ヵ月以内」に全ての必要書類を集めて提出しなければいけません。
「自力だとミスをしそうで不安」「役所や裁判所に出向く余裕がない」というような人は、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に手続きを代行してもらうことで、自力で対応する手間が省けますし、ミスなくスムーズに相続放棄を済ませることができます。
相談だけであれば無料の事務所などもあるので、まずは一度相談しましょう。