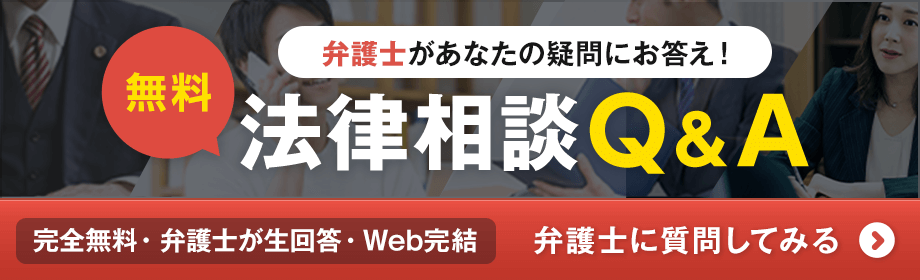- 自分は独身だけど、自分の財産は誰が相続することになるの?
- 独身の兄弟が亡くなったときは誰が相続人になるの?
- 独身の子どもが先に亡くなった場合の相続はどうなる?
独身の家族や親族が亡くなった場合、遺産を誰が相続するのかで悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、独身の遺産は誰が相続するのかについて、相続人がいる場合といない場合のケース別に紹介します。
あわせて、法定相続の相続順位についても解説するので、参考にしてください。
|
優先順位
|
法定相続人がいる場合
|
法定相続人がいない場合
|
|
1
|
直系卑属(子、子が先に死亡している場合で孫がいる場合は孫)
|
債権者
|
|
2
|
直系尊属(父母、父母が先に死亡している場合で祖父母がいる場合は祖父母)
|
特定受遺者
|
|
3
|
兄弟姉妹
|
特別縁故者
|
|
4
|
―
|
財産の共有者
|
|
5
|
―
|
国庫
|
|
備考
|
【遺言書がない場合】
・最上位の法定相続人が全財産を相続する
・最上位の法定相続人が複数いる場合は人数で按分する
【遺言書がある場合】
・遺留分を侵害しない範囲で遺言書の内容が優先される
|
・相続財産管理人が選任された後、清算手続きに則って、上位から優先して清算・分配される
|
独身の方で相続をどうするべきかお悩みの方へ
自身が独身の場合、自身の遺産を誰が相続するのかわからない...と悩んでいませんか?
結論からいうと、基本的には独身者の法定相続人が相続することになります。
ただし、自分の意思を反映した遺産の分配をしたい場合は、遺言書の作成をする必要があります。
法的に有効な遺言書を作成したい場合は、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
弁護士に相談することで以下のようなメリットを得ることができます。
- 遺言書を作成するべきかどうかがわかる
- 依頼すれば、スムーズに遺言書を作成することができる
- 依頼すれば、相続問題全般について相談できる
当サイトでは、遺言書の作成をはじめとした相続問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。
独身者の遺産は基本的に法定相続人が相続する

まず独身者の「法定相続人」について確認しましょう。
法定相続人とは民法で定められた相続人のことです。
特に遺言書などがなく、法定相続人がいる場合は、被相続人の財産は法定相続人がその法定相続分に応じて承継します。
この法定相続人には範囲と優先順位が定められています。
配偶者は常に相続人となり、その配偶者に加えて、優先順位が最も高い法定相続人が財産を承継します。
独身者の場合、当然ながら配偶者はいないので、以下のうち最も優先順位が高い法定相続人が財産を受け取ります。
|
相続の順位
|
法定相続人
|
|
第1順位
|
直系卑属(子・孫)
|
|
第2順位
|
直系尊属(父母・祖父母)
|
|
第3順位
|
兄弟姉妹
|
第1順位:子ども|独身者(配偶者とは死別・離婚)の直系卑属が相続

離婚や死別、内縁関係など、被相続人が相続開始時に独身者だとしても、子どもがいる場合があります。
独身者に子どもがいる場合には、まずその子どもが相続人です。
仮にその子どもが被相続人よりも先に亡くなっていた場合、孫が代襲者として相続人となります。
これを代襲相続といいます。
子どもが複数いる場合はその子どもの人数で按分します。
第2順位:父母|独身者(配偶者とは死別・離婚)の直系尊属が相続

子どもや代襲者がいない場合、被相続人の直系尊属が相続人となります。
被相続人の直系尊属とは、被相続人の父母や祖父母のことです。
ただし、被相続人の祖父母が健在であっても、被相続人の父または母のいずれか一方が健在の場合、被相続人の祖父母は相続人とはなりません。
両親ともに健在の場合にはそれぞれ2分の1ずつが法定相続分となります。
なお、両親が離婚していて、親権を有していない親であったとしても、被相続人の法定相続人です。
第3順位:兄弟・姉妹|配偶者とは死別・離婚、直系卑属(子や孫)はいない、直系尊属(父母も祖父母)もいない場合

直系卑属や直系尊属がいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、その子どもである甥や姪が代襲者として相続人となります。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続は、直系卑属の場合と異なり、一代までと決まっているので、再代襲(甥や姪の子どもによる代襲)は起こりません。
この場合も、兄弟姉妹が全ての財産を相続する形となります。
兄弟姉妹が複数いる場合にはその人数で按分します。
独身者の相続人は誰になる?具体例を用いて解説
ここからは、独身者が亡くなった際の相続人が誰になるのかを具体例を用いて解説します。
なお、ここでは被相続人には法定相続人がいることを前提とします。
独身の兄弟が亡くなったときの相続人
独身の兄弟が亡くなった場合は、まずその子どもや孫が相続人となります。
子どもや孫がいない場合は、直系尊属(被相続人の親・祖父母など)が相続人となり、親や祖父母などもすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続をすることになります。
このように独身の兄弟が亡くなっても、兄弟である自分が必ずしも相続できるわけではないので注意しましょう。
独身の子どもが亡くなったときの相続人
独身の子どもが亡くなった場合は、まずその子どもや孫が相続人となり、子どもや孫がいない場合は、被相続人の親が相続することになります。
独身者に子や孫がいる場合には、その子や孫が第1順位の相続人となりますが、独身者に子や孫がいない場合は親であるあなたが相続権を得ることを覚えておきましょう。
ただし、独身であっても、子を認知している場合には、その子が被相続人の第1順位の相続人となり、親には相続する権利がありません。
特に、親子関係が希薄な場合などは、戸籍を確認して被相続人において認知している子がいないか確認することも必要でしょう。
独身者で法定相続人がいない場合は?

法定相続人が全くいない場合、利害関係人や検察官からの申し立てにより相続財産管理人が選任されたあとに、以下の順番で遺産を清算・分配することになります。
遺産の清算・分配の流れ
- 債権者への支払いに充てる
- 特定受遺者が承継する
- 特別縁故者が承継する
- 財産の共有者
- 国庫に帰属
①債権者への支払いに充てられるケース
相続財産人管理人が被相続人の債権者を探し、各債権者の債務に対する支払いをおこないます。
たとえば被相続人が金銭を借りている場合や家賃や光熱費、携帯電話代などの支払いが未払いの場合、まず優先的にそれらの支払いがおこなわれます。
②遺言で指定された特定受遺者が承継するケース
遺言により財産を渡すことを「遺贈」といい、遺贈により財産を受け取る人のことを特定受遺者といいます。
この遺贈は相続人に対しても、相続人以外の人に対してもおこなうことができます。
つまり独身者で法定相続人がいないという場合に、その独身者は、遺贈によって、お世話になった人など特定の者に、自分の意思で財産を承継させることが可能です。
ただし、遺言で遺贈をおこなう際には、以下のような相続税には注意が必要です。
相続税額の「2割加算」に注意
相続税の2割加算とは、文字通り相続税額に相続税の2割に相当する金額が加算されるものです。
相続や遺贈によって財産を取得する人が被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額に相続税の2割に相当する金額が加算されます。
たとえば、以下のような人が遺産を取得する場合は、2割加算の対象となるため注意しましょう。
2割加算の対象となる受贈者
- 兄弟姉妹
- 甥姪
- 祖父母
- 代襲相続人ではない孫
- 被相続人の養子となった孫
- 内縁の夫や妻
③特別縁故者が承継するケース
相続人や特定受遺者ではなくても、被相続人と同一生計にあった人や被相続人の療養看護に務めた人なども相続財産を受け取ることができる場合があります。
そのような人のことを特別縁故者といいます。
特別縁故者として認められるのは以下のケースです。
特別縁故者として認められるケース
- 療養看護をしていた人
- 被相続人と生計を同じくしていた人(内縁関係など)
- 特別の縁故があった人(親代わりなど)
また、被相続人が生前に関わりの深かった「法人」なども特別縁故者として認められる場合があります。
ただし、特別縁故者になるには、相続人不存在が確定したあと3ヵ月以内に相続財産分与の申し立てをおこなう必要があります。
④財産の共有者に帰属するケース
不動産などを自分以外の人と共有名義にしているケースもあるかもしれません。
この点に関しまして、民法255条は、共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属すると定めています。
ただし、本条の適用に関し、最高裁は、相続人がいないだけでなく、債権者・特別受遺者・特別縁故者のいずれも存在しない、あるいはそれぞれに対する清算や分配が済んでなお財産が残っている場合に、本条により他の共有者に帰属すると判断しています(最判平成元年11月24日)。
⑤国庫に帰属するケース
債権者、特定受遺者、特別縁故者、財産共有者がいずれもいないか、それぞれへの清算・分配が済んでも余りがある場合、残った財産は最終的に国のものとなります。
相続人のいない独身者の相続で重要な「相続財産管理人」とは
相続人のいない独身者の遺産の分配や帰属に関しては、相続人がいないわけなので、分配や帰属を受ける人やその順位を調査・決定し、また、その決定に従って相続財産を管理・処分する役割を担う存在が必要です。
相続人がいない場合に、遺産の取得者・帰属者を確認し、分配や帰属のための処理をおこなう人のことを相続財産管理人といいます。
相続財産管理人は、利害関係人や検察官からの申し立てを受け、家庭裁判所によって選任されます。
多くの場合、弁護士が選任されます。
相続人がいても、財産のなかに借金などのマイナスの財産が多く、相続人全員が「相続放棄」をしたようなケースでは、債権者により相続財産管理人の選任申立てがおこなわれることもあります。
相続財産管理人による一連の業務は以下のとおりです。
相続財産管理人の業務
- 相続財産や相続人の有無の調査
- 被相続人の債務の清算
- 特別縁故者への財産分与
- 相続財産を国庫に帰属
独身者がやっておきたい相続の生前対策3つ
独身者がやっておきたい相続生前対策を3つ紹介します。
1.遺言書を作成する
独身者の方の相続対策として一番大切なことは、遺言書を作成しておくことです。
遺言書を残すことで自分の財産を誰に渡すのか、意思を明確にし、その意思に沿った遺産の分配や帰属を実現することができます。
遺言書にもさまざまな様式があり、書き方のルールが法律上厳格に定められています。
そのため、書き方の不備によっては遺言が無効となってしまうケースもありますので注意しましょう。
たとえば自筆証書遺言の場合、以下のような遺言は無効とされてしまいます。
遺言書が無効になりやすいケース
- 自書でないもの
- 日付がないもの
- 財産の特定が不明確なもの
さらに、遺言者が認知症などの影響により、遺言の内容を理解し、その遺言によって自分の相続がどのようになるのかを理解することのできる能力(遺言能力)がない状況で作成した場合においても、遺言書は無効となってしまいます。
現に、相続人間で、遺言者の遺言能力が争われ、これが否定されたために、遺言書自体が無効とされた事例も多数存在します。
自筆証書遺言よりも公正証書遺言を作成する
自分の死後、相続人間で遺言書の有効性を巡る無用なトラブルを避けたいと考える人も多いことでしょう。
その考える場合には、自筆証書遺言ではなく、公証人に依頼をして「公正証書遺言」として作成することが有用です。
また、遺言書によって、法定相続分と異なる相続分を設定する場合や、法定相続人がいる場合、法定相続人以外に財産を渡そうとする場合には、「遺留分」という法定相続人に最低限保障された財産承継の権利にも配慮する必要があります。
たとえば、被相続人が法定相続人以外の人物に自分の財産全部を遺贈したとしても、法定相続人はこの遺贈により全財産を譲り受けた人物に対して、「遺留分」という一定の金額を請求することができます。
以下の記事では、遺言書の種類や書き方について詳しく解説しています。
自身の相続に備え、遺言書の作成を考えている方はぜひ参考にしてください。
公正証書遺言作成の流れ
相続人間で遺言書の有効性を巡る無用なトラブルを避けるには公正証書遺言を作成することをおすすめします。
公正証書遺言とは、公証人という法律の専門家が関与して作成する遺言書で、以下のような特徴があります。
● 確実性が高い:形式的な不備がなく、偽造・変造が難しい
● 紛失リスクがない:原本は公証役場で保管
● 検認不要:相続開始後すぐに手続きできる
● 費用がかかる:数万円程度
また、公正証書遺言には以下のようなメリット・デメリットがあります。
|
メリット
|
デメリット
|
|
トラブルが少ない:法律的に有効な遺言書として認めやすい
安心できる: 専門家が作成に関与
|
自分で書けない:公証人に依頼する必要がある
費用がかかる:自筆証書遺言より高額
|
独身者の相続の場合、相続人同士での争いが発生する可能性もあるので、メリットデメリットを踏まえて、事前に公正証書遺言を作成しておくのも手でしょう。
公正証書遺言作成の流れ
ここでは、具体的に公正証書遺言の流れについて解説します。
公正証書遺言は以下の流れで作成することになります。
|
作成の流れ
|
具体的な手続き内容
|
|
1.公証人への相談・依頼
|
電話、メール、来所などで予約
相談内容を伝え、必要書類を確認
|
|
2.遺言内容の検討
|
誰に何を相続させるか具体的に検討
遺言執行者を指定するかどうか決める
|
|
3.公証人との事前協議
|
遺言内容について公証人と協議
必要があれば案文を作成してもらう
|
|
4.作成日時の調整・証人の選定
|
公証人との日程を調整
2名以上の証人を依頼
|
|
5.作成当日
|
本人確認書類を持参して公証役場へ
公証人が遺言内容を読み上げ、確認
遺言者、証人、公証人が署名・押印
|
|
6.作成完了
|
公正証書遺言の原本は公証役場が保管
遺言者には謄本(写し)が交付
|
公正証書遺言は、弁護士に相談することでスムーズに作成することができます。
弁護士は法律の知識と経験に基づき、遺言書の内容をチェックします。
また、将来的な相続トラブルを未然に防ぐためのアドバイスもしてくれるので、満足いく遺言書を作成することができるでしょう。
まとめ
独身者の相続に関しては、法定相続人がいれば、民法の定めるルールに従って、法定相続人に対し、法定相続分に応じた遺産の承継がおこなわれます。
他方、法定相続人がいない独身者の場合には、相続財産管理人によって債権者・受遺者・特別縁故者などに対し、遺産の清算・分配がおこなわれます。
そして、とくに法定相続人のいない独身者の場合には、遺言書を作成しておくことで、相続財産管理人の選任などを要することもなく、被相続人が自分の意思を反映した遺産の帰属や分配を実現することができます。
遺言書に自分の思いを正確に反映し、これを有効に機能させるために、遺言書に詳しい弁護士に作成を依頼することもご検討ください。
独身の方で相続をどうするべきかお悩みの方へ
自身が独身の場合、自身の遺産を誰が相続するのかわからない...と悩んでいませんか?
結論からいうと、基本的には独身者の法定相続人が相続することになります。ただし、自分の意思を反映した遺産の分配をしたい場合は、遺言書の作成をする必要があります。
法的に有効な遺言書を作成したい場合は、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
弁護士に相談することで以下のようなメリットを得ることができます。
- 遺言書を作成するべきかどうかがわかる
- 依頼すれば、スムーズに遺言書を作成することができる
- 依頼すれば、相続問題全般について相談できる
当サイトでは、遺言書の作成をはじめとした相続問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。