 相続に関する弁護士相談をご検討中の方へ
相続に関する弁護士相談をご検討中の方へ
贈与契約書(ぞうよけいやくしょ)とは、確実に贈与があったことを第三者や税務署などに証明できるように、贈与者と受贈者の間で結ぶ書面のことです。
贈与をする際、あまり贈与契約書の存在を意識することは少ないかもしれませんが、贈与契約書があることで税務署から突っ込まれるリスクを回避できるなどのメリットがあるため、作成しておくことをおすすめします。
本記事では、贈与契約書の書き方やひな形、贈与契約書を作成するメリットなどを解説します。
|
生前贈与について 弁護士に相談するメリットとは? |
|
生前贈与は、相続前に財産を減らすことで、節税効果が期待できるという大きなメリットがある一方、相続人の間におけるトラブル原因にもなりやすいです。
その点、弁護士は、相続トラブルを解決する立場にあるため、生前贈与絡みの案件も扱うことが多く、豊富な経験を元に「どのような策をとればよいか」アドバイスをすることが可能です。
・生前贈与に関する相続トラブルを未然に防ぎたい ・生前贈与が絡んだ相続トラブルに悩んでいる
このような方は、まず無料相談などを気軽に活用してみましょう。 |
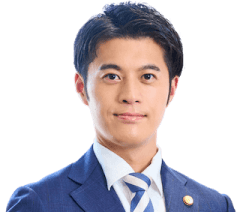
まずは、贈与契約書を作成する必要性やメリットについて紹介します。
民法550条では、書面を残さない贈与は撤回できるとされています。
したがって、贈与者が口頭で「贈与をしたい」という旨を受贈者に伝えても、受贈者側が単独でその契約を撤回できてしまうのです。
贈与者が確実に贈与をしたいという意思があるならば、必ず書面にてその意思を残しておく必要があります。
そこで重要となるのが贈与契約書です。
(書面によらない贈与の撤回)
第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
引用元:民法第550条
贈与する際は、生前から少しずつ子どもや孫などに財産を渡していく「暦年贈与」という方法があります。
生前贈与については、毎年1月1日から12月31日までの贈与額が110万円までであれば贈与税が非課税になります。
ただし、毎年同じ時期に継続して贈与していると、税務署から「最初からまとまった贈与をするつもりだった」とみなされる可能性があります。
そのような場合、それまで110万円の非課税範囲内で贈与してきた財産に贈与税がかかる事態にもなりかねませんが、あらかじめ贈与契約書を作成しておけば「まとめて贈与している」などといわれるような事態を防ぐことができます。
名義預金とは、親族に名義を借りて預金していることをいいます。
たとえば、税務署では名義預金について以下のようなやり取りがおこなわれることもあります。
贈与について、生活費などを渡すことは贈与税の対象にはならないのが通常です。
ここでいう生活費とは「その人にとっての通常の日常生活に必要な費用」のことをいいますので、それを預金したり株式や不動産などの購入資金に充てたりする場合には、贈与税がかかるとされています。
つまり、夫婦間の贈与でも貯金をしていると贈与税の扱いになりますし、孫への贈与でも同様です。
名義預金とされないためには、「いつでも受贈者本人が口座からお金を引き出せる状態である」という事実が必要ですし、都度契約書に残しておくことが大切です。
名義預金として課税対象になることを防ぐことについて、より詳しく知りたい場合は「名義預金として相続税の課税対象になる事を防ぐ3つの方法」を確認してください。

次に、贈与契約書にどのようなことを書いておくべきなのか、サンプルと一緒に見ていきましょう。
贈与契約書を自分で作成するときは、以下のポイントに気を付けましょう。
この7項目を念頭において作成すれば、基本的には問題ないでしょう。
|
贈 与 契 約 書 贈与者 アシロ太郎(以下「甲」という)は、受贈者 アシロ花子(以下「乙」という)と、下記条項により贈与契約を締結する。 記 第1条 甲は、現金500万円を乙に贈与するものとし、乙はこれを受諾した。 令和__年__月__日 (甲)住所 東京都新宿区●—●●—●● (乙)住所 東京都新宿区●—●●—●● |
|
贈 与 契 約 書 贈与者 アシロ太郎(以下「甲」という)は、受贈者 アシロ花子(以下「乙」という)と、下記条項により贈与契約を締結する。 記 第1条 甲は、甲の所有する下記の財産を乙に贈与するものとし、乙はこれをした。 第2条 甲は、第1条に基づき贈与した財産を、20●●年●●月●●日までに、乙へ引き渡し、かつ、本件不動産の所有権移転登記手続をおこなう。 令和__年__月__日 (甲) 住所 東京都新宿区●—●●—●● (乙) 住所 東京都新宿区●—●●—●● |
|
贈 与 契 約 書 贈与者 アシロ太郎(以下「甲」という)は、受贈者 アシロ花子(以下「乙」という)と、下記条項により贈与契約を締結する。 記 第1条 甲は、甲の所有する下記の財産を乙に贈与するものとし、乙はこれを受諾した。 第2条 甲は、第1条に基づき贈与した財産を、20●●年●●月●●日までに、乙へ引き渡すものとする。 令和__年__月__日 (甲) 住所 東京都新宿区●—●●—●● (乙) 住所 東京都新宿区●—●●—●● |

次に、贈与契約書を作成する際や、贈与をおこなう際の注意点を紹介します。
不動産などを贈与するときは、200円分の収入印紙を貼る必要があります。
印紙代は不動産額によって異なるので、場合によっては200円以上かかるケースもありますが、贈与をする際に金額を記載しなければ200円分の収入印紙を貼っておけば問題ないとされています。
全部パソコンなどで作ってしまうと、本人以外でも作成できてしまう契約書になります。
「本当に本人が契約したもの」という信憑性をもたせるためにも、署名は自筆しておくのが良いでしょう。
毎年繰り返し贈与をおこなうことで「定期贈与であった」とみなされる危険性もあるので、下記のような対策をしておくとよいでしょう。
贈与がおこなわれてから一定期間内に贈与者が亡くなってしまうと、贈与財産は相続税の課税対象となってしまいます。
2023年12月31日までにおこなわれた贈与については「亡くなる3年前までの贈与」が課税対象となり、2024年1月1日以降の贈与については「亡くなる3年前から7年前までの贈与」が課税対象となります。
贈与をおこなう際は贈与日を明確にしておくほか、課税対象になるリスクを回避するためにも、なるべく早いうちに契約を交わしておくことをおすすめします。
以下のようなケースでは、司法書士や税理士などに贈与契約書の作成を依頼することをおすすめします。
不動産の贈与では、贈与税の基礎控除額である110万円を超えるケースが一般的です。
そのため、贈与する際は暦年贈与よりも「相続時精算課税制度」や「配偶者控除」などを利用するのが良いでしょう。
なお、贈与契約・登記・贈与税の申告などの手続きが必要になるため、手間なくスムーズに済ませたい場合は司法書士や税理士などに贈与契約書の作成を相談・依頼することをおすすめします。
依頼費用について心配な方は「税理士に依頼した場合の費用の相場と税理士報酬の考え方まとめ」を確認してください。
過去分の贈与について贈与契約書を作成すると、税務署から税金逃れとみなされる可能性があるため、あまりおすすめはできません。
もしどうしても作成したい場合は、税理士などにどのような内容で作成すればよいか相談しましょう。
株式を贈与する場合、たとえば同族会社の株式が贈与されると「法人税申告書」「株主名簿」などの書類名義が変更になって手続きが面倒になるため、このようなケースでも相談したほうが良いでしょう。
これらのケース以外でも、少しでも迷うことがあればまずは専門家に相談してみることをおすすめします。
贈与契約書は、確実に贈与を済ませるためにも必要な書類です。
ただし、作成時は贈与内容などを漏れなく記載する必要があり、自力では不安な場合は司法書士や税理士などにサポートしてもらうことをおすすめします。
なかには初回相談無料のところもあるので、まずは一度詳しく話を聞いてみましょう。


生前贈与は贈与税を削減するための最も有効な方法ですが、時に贈与税がかかる場合もありますので、今回は非課税とさせる方法をご紹介します。
不動産の生前贈与が贈与税を抑えることに繋がるとして最近注目されている手法ですので、今回は生前贈与で不動産を贈与する際の税金対策をご紹介します。
土地の贈与税を計算するにはいくつか方法があるものの、正直よくわからない部分も多いと思いますので、今回は土地の贈与税の計算とご紹介していきます。
生前贈与は税金対策として有効な手段のひとつですが、対応を誤ると贈与税がかかる場合もあります。この記事では、生前贈与で税金の負担を抑える方法や、贈与税の税率や計算...
本記事では、贈与税の申告方法や必要書類、申告漏れがあった場合の罰則や、申告内容に誤りがあった場合の修正方法などを解説します。これから贈与税の申告をしようと考えて...
生前贈与(せいぜんぞうよ)とは、その名のとおり『生きている間に財産を誰かに贈る』法律行為です。贈与はいつでも・誰でもできるものですが、その中でも特に利用しやすく...
この記事では、生前贈与により遺留分を侵害されている方に向けて、受贈者に対して遺留分侵害額請求ができるかどうか、遺留分の割合や遺留分侵害額の計算方法などの基礎知識...
遺産相続の際に遺産を受け取る人を相続人と言いますが、この相続人には遺産をもらえる順番というものがありますので、今回は孫に遺産を残す3つの方法をご紹介します。
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母・祖父母が18歳以上の子ども・孫に財産を贈与する際、2,500万円までは贈与税がかからない制度です。この記事では、相続時...
贈与税には時効があります。つまり、贈与税の時効を超えると納めるべき贈与税が消滅するのです。しかし、簡単に国の税金から逃れられない仕組みがあります。
孫への生前贈与は基本的に持ち戻し7年ルールの対象外です。しかし、生前贈与の方法によっては、贈与税や相続税が発生します。本記事では、持ち戻しルールや孫への生前贈与...
マンションの贈与は原則として贈与税の課税対象ですが、税金の制度は複雑なので実際にいくらかかるのか、節税できないのかなど、さまざまな疑問を抱えている方も多いはずで...
婚姻期間が20年以上の夫婦が利用できるおしどり贈与には、メリットもあればデメリットもあります。そこで本記事では、おしどり贈与を利用するための3つの要件や、利用す...
特別受益とは、一部の相続人だけが被相続人から特別に得ていた利益のことです。生前贈与や遺贈が特別受益と認められれば、相続財産に加算され、公平な遺産分割をおこなうこ...
親が子供に車を買ってあげる場合、相続税対策でおこなうような生前贈与と同様に贈与税が問題となります。どのような場合に贈与と評価されるのか、贈与と評価されて贈与税が...
暦年贈与をおこなうことで節税効果が期待できますが、贈与の仕方によっては贈与税や相続税が課税されることもあります。本記事では、暦年贈与のメリットや税制改正による変...
預貯金の生前贈与は、相続税対策として有効な手段です。しかし、生前贈与と認められるためには「名義預金」とみなされないよう注意する必要があります。本記事では、預貯金...
死因贈与契約書とは、自分の死後に財産を受け取って欲しい人と契約する贈与契約です。遺言書とは異なり、両者の合意が必要な点が大きな違いです。本記事では、死因贈与契約...
他人から財産を贈与された場合は、贈与税が課されるのが原則です。両親や祖父母などから贈与を受けようとする際には、贈与税の非課税限度額を理解しておきましょう。本記事...
相続人が被相続人から受けた遺贈や贈与は「特別受益」に当たり、相続財産への持ち戻しの対象となります。本記事では特別受益の持ち戻し免除について、方法・注意点・トラブ...

