
 遺産分割に関する弁護士相談をご検討中の方へ
遺産分割に関する弁護士相談をご検討中の方へ
数次相続(すうじそうぞく)とは、被相続人の遺産相続が開始したあと、「遺産分割協議」や「相続登記」を行わないうちに相続人の一人が死亡してしまい、次の遺産相続が発生してしまうことをいいます。
父親の相続財産についての遺産分割協議は、相続人である母親と子ども達でおこないます。
しかし、この協議の前に母親が亡くなってしまった場合、残された子どもたちは父親の相続財産についての遺産分割協議だけでなく、母親の財産の遺産分割協議をおこなう必要があります。
そして、理論上は、母親の相続財産の中には、相続するはずであった父親の相続財産も含まれるということになります。
つまり、子どもたちのおこなう遺産分割協議には、父→母→子という2回の相続分が含まれるということになり、このような相続が2回以上重なっている状態を数次相続といいます。
今回は、この数次相続についての法律知識をご紹介します。
数次相続でお困りの方へ
数次相続の問題解決を弁護士に依頼する事で、以下のようなメリットがあります。
;当サイト『ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)』は相続争いの解決を得意とする弁護士を掲載しております。
電話での相談や初回相談を無料にしている事務所もありますので、まずは下記からお気軽にご相談ください。
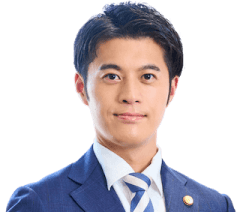

数次相続(すうじそうぞく)とは、被相続人の遺産相続が開始したあと、遺産分割協議が終わらないうちに相続人の一人が死亡してしまい、次の遺産相続が発生してしまうことをいいます。
数次相続では、最初に発生した相続を「一次相続」、次に発生した相続を「二次相続」と呼び、一次相続の相続人が亡くなった場合は、本来その相続人が受けとるはずだった相続分を、二次相続の相続人が引き継ぎます。

上記の図は簡単な数次相続の例です。
本人は子がいないため、その相続(1次相続)の法定相続人は妻(配偶者)と母(直系尊属)です。
しかし、遺産分割協議が未了のまま母が死亡したため本人の財産について2次相続が発生した例です。
本人の財産について本来は兄と妹は相続人となりません。
しかし、母が死亡したことで、本人の相続財産中の母の相続分は、母の相続人である子(兄、妹)が相続します。
結果、本人の相続財産の一部については、妻(配偶者)だけでなく兄、妹の3人で遺産分割が必要ということになります。
⇒母の一次相続の相続分3分の1についても、兄と妹が2分の1ずつ相続することになります。

上図は3次相続の説明図です。祖父は平成1年に死亡(1次相続開始)。
遺産分割が未了のまま父が平成20年に死亡(2次相続開始)。
更に遺産分割が未了のまま平成28年に本人が死亡(3次相続開始)。
この状態で遺産分割協議をするという例です。
祖父死亡の相続開始による法定相続人と法定相続分は、配偶者である祖母4/8、子である伯父、父、叔母、前妻の子の伯母はそれぞれ1/8となります。
父死亡の相続開始による法定相続人と法定相続分は、配偶者である母3/6、子である兄、本人、弟はそれぞれ1/6を相続します。
本人死亡の相続開始による法定相続人と法定相続分は、配偶者である夫3/6、前婚の子A、後婚の子B、子Cはそれぞれ1/6となります。
結果、祖父の死亡については、祖母、伯母、伯父、母、叔母、兄、弟、夫、子A、子B、子Cの11名で、父の死亡については、母、兄、弟、夫、子A、子B、子Cの7名で、本人の死亡については夫、子A、子B、子Cの4名で、それぞれ分割協議が必要です。
これを見れば相続処理が極めて煩雑となることは容易に想像できると思います。
たとえば、祖父の財産について、夫は会ったこともない複数の親族との間で協議する必要があります。
また、法定相続分も、祖母は144/288、伯母・伯父・叔母は各36/288、母は18/288、兄、弟は各6/288、夫は3/288、子A、子B、子Cは各1/288と、非常に細分化されます。
このように、その都度遺産分割をしておかないと、相続人の範囲はどんどん拡大し、遺産分割協議の話合いが事実上不可能となったり、実施されても協議がまとまらないということが考えられます。

数次相続は「遺産分割協議を終える前に相続人が死亡し、新たな相続が開始する」という状態をいい、代襲相続は「生きていれば相続人だった」者の子どもがその人に代わり相続人になる、という状態をいいます。
代襲相続とは、父親が死んで子どもが相続人となるはずが、子どもは父親より先に死んでしまってすでにいないので、先に死んだ子どもに代わって孫が相続人になる、というものですので、数次相続と代襲相続の違いは、亡くなった順番の違いによるもの、ということがいえます。

下記の例を参考に、数次相続における相続登記の手続きをみていきましょう。
この場合、普通なら息子(アシロ太郎)と息子(アシロ二郎)が法定相続分に従って、半分ずつ相続しますが、祖父の死んだ後、息子(アシロ太郎)も死亡してしまったケースにおいては、祖父が死んだときに第一の相続、息子(アシロ太郎)が死んだときに第二の相続が発生するという流れです。
つまり各相続分は、
となるはずです。
仮に、アシロ二郎が相続放棄をして相続人にならなかった場合は
となります。
なお、実務上は最初に死んだ人から順に、最後の相続人へ所有権移転登記(相続登記)することができます。
そのため、後者の例で遺産分割協議がまとまれば
という直接的な相続登記が可能です。
たとえば、第一の相続で祖父から直接受け継ぐべき相続人が一人の場合です。
この、「中間が単独」というのは、元々相続人が一人の場合だけではなく、相続人が複数いても、相続放棄や、その他、遺産分割、特別受益者がもらうべき相続分がないような場合も含まれます。
上記の例で1次相続開始後に長男と長女が2分の1ずつ相続するとの遺産分割協議がおこなわれたとします。
その後、相続登記前に2次相続が開始され、長男相続分の2分の1を長男妻が単独で相続するとの遺産分割協議がおこなわれました。
この場合、最終的には長女2分の1、長男妻2分の1の共有名義になります。
しかし、1次相続で単独相続がおこなわれていないため、たとえ2通の遺産分割協議書を添付しても被相続人Aから、長女および長男妻への直接の相続登記することはできません。
そのため、被相続人Aから、長女および長男への相続登記後、長男から長男妻への相続登記をおこなう必要があります。
このように、1次相続が単独相続でない場合、最終相続人に直接の相続登記することはできません。
遺産相続における数次相続に関する内容は以上になります。
相続人が遺産分割協議中に死亡した場合などあまりないケースかと思われがちですが、いつそういったことが起るかは誰にもわかりません。
もしあなたが数次相続の場面に出くわした場合は、焦ることがないように準備しておくことをおすすめします。


相続が発生したとき、配偶者は必ず相続人となり、その他の相続人は子ども、父母、兄弟姉妹の順に相続順位が決まります。 相続順位の基本ルールや、「だれがどれくらいも...
遺産相続にあたって遺産分割協議書をどのように作成すればよいのか、悩んで方も多いのではないでしょうか。本記事では、遺産分割協議書の必要性や具体的な書き方を解説しま...
親等は親族関係の近さを表したものです。この記事では親等とは何か、親等をどうやって数えるかといった基本的なことのほか、親等早見表、親等図を記載しています。親等でよ...
兄弟姉妹が亡くなり、兄弟姉妹に親や子どもがいない場合には、残された兄弟姉妹が遺産を相続することになります。そこで、本記事では相続における兄弟姉妹の相続順位や割合...
法定相続人の順位が高いほど、受け取れる遺産割合は多いです。ただ順位の高い人がいない場合は、順位の低いでも遺産を受け取れます。あなたの順位・相続できる遺産の割合を...
特定の相続人に遺産を相続させない方法を知りたくはありませんか?夫・妻・兄弟はもちろん、前妻の子・離婚した子供に財産・遺留分を渡したくない人は注目。悩み解消の手助...
費用の目安やケース別の費用例を詳しく解説。相場より高額になるケースや弁護士費用を払えないときの対処法も解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
株式の相続が発生すると、株式の調査や遺産分割、評価や名義の変更などさまざまな手続きが必要になります。この記事では、株式を相続するときの手順について詳しく解説しま...
亡くなった家族に確定申告が必要だった場合、準確定申告書の提出が必要です。この記事では準確定申告書と付表の書き方を記入例付きで詳しく解説します。
遺産分割協議とは、相続人全員による遺産分割の話し合いです。この記事では、遺産分割協議の進め方や、不動産など分割が難しい財産の分配方法などを解説するとともに、話し...
相続人申告登記は、遺産分割協議がまとまらない際に過料を免れるための有効な制度です。ただし、結局は相続登記が必要となるので、二度手間になる可能性があります。利用す...
叔父や叔母が亡くなった場合、例外的に甥や姪が法定相続人になると法定相続分の計算が複雑になったり、一般的に相続手続きとは異なる点があります。本記事では、叔父や叔母...
特別受益とは、一部の相続人だけが被相続人から特別に得ていた利益のことです。生前贈与や遺贈が特別受益と認められれば、相続財産に加算され、公平な遺産分割をおこなうこ...
遺産分割協議書の作成方法がわからないという方もいるでしょう。また、今後相続登記をする場合、遺産分割協議書を含めたさまざまな書類が必要になることも考えられます。こ...
本記事では、相続人の中で被相続人から贈与などの利益を受け取った特別受益者について解説します。特別受益者の定義や特別受益にあたる贈与の種類、さらに相続人の中に特別...
相続人の中に未成年者や認知症などで判断能力が低下してしまっている方がいる場合、遺産分割協議をおこなうに際に特別代理人の選任が必要となる場合があります。本記事では...
生前、被相続人に対して一定の貢献を果たした相続人は、遺産相続の際に「寄与分」を主張することができます。本記事では、遺産相続で寄与分の主張を検討している相続人のた...
遺産相続は、資産の特定や分け方などが複雑で、金額や相続人が多いほどたいへんです。本記事では、配偶者になるべく多くの遺産を相続させたい場合にできる適切な準備などに...
遺産分割は共同相続人全員でおこなう必要があり、遺産分割に先立って漏れなく共同相続人を把握しなければなりません。本記事では、共同相続人とは何か、および共同相続人に...
家庭裁判所の調停委員が、相続人全員が遺産分割方法など合意を形成できるようなアドバイス・和解案を提示。遺産分割調停を控えている方や、遺産分割協議が思うように進まず...

