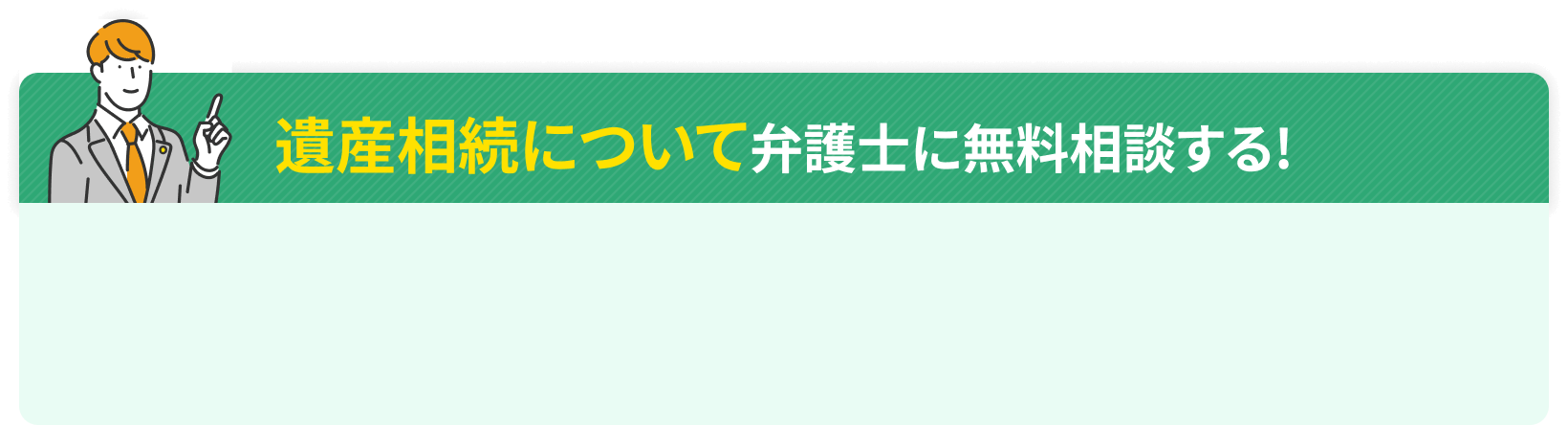被相続人が借地権を有していた場合、現金や預貯金などと同様に相続財産として相続人に引き継ぐことができます。
基本的に借地権の相続では地主の許可は不要ですが、例外的に許可が必要で承諾料がかかるケースもあり、地主との間でトラブルになることもあります。
また、借地権の相続では相続税の計算なども必要で、トラブルやミスなく相続手続きを済ませるためにも本記事で正しい対応方法を押さえておきましょう。
本記事では、借地権の相続手続きや地主の許可が必要なケース、相続税を申告する際の計算方法やよくあるトラブルの対処法などを解説します。
借地権の相続でお悩みの方へ
「借地権が関わる遺産相続、地主とトラブルなく穏便にできたらいいな...」と悩んでいませんか?
結論からいうと、借地権の相続で悩んでいるなら弁護士に相談・依頼するのがよいでしょう。なぜなら、あなたの状況に合わせて法的に有効なアドバイスを受けられるからです。
弁護士に相談することで以下のようなメリットを得られます。
- 地主と起きているトラブルについて相談できる
- 地主とのトラブルを避けるコツがわかる
- 借地権の遺贈手続きの対応方法がわかる
- 更新料や地代の値上げなどの悩みを相談できる
当サイトでは、相続について無料相談できる弁護士を多数掲載しています。電話での相談も可能なので、依頼するか決めていなくても、本当に弁護士に依頼すべきかも含めてまずは無料相談を利用してみましょう。
借地権とは?
借地権とは、建物を建てる目的で第三者の土地を借りる権利のことです。
借地権は「普通借地権」と「定期借地権」の2つに分類され、どちらに該当するかによって相続税申告時の評価方法が異なります。
以下では、それぞれの定義や特徴について解説します。
普通借地権
普通借地権とは、契約の更新が可能な借地権のことです。
借主である借地人が契約更新を希望した場合、地主は正当な理由がないかぎり拒否することができません。
普通借地権の存続期間は原則として30年で、初回更新後の存続期間は20年、2回目からは10年となります(借地借家法第3条、第4条)。
定期借地権
定期借地権とは、契約の更新ができない借地権のことです。
普通借地権とは異なり、事前に決めた存続期間が満了すると必ず契約終了となり、建物を取り壊して土地を更地の状態にして地主に返還しなければいけません。
定期借地権はさらに3種類に細分化され、それぞれ存続期間は以下のように異なります。
- 一般定期借地権(一般的な定期借地権):50年以上
- 事業用定期借地権(事業用の定期借地権):10年以上50年未満
- 建物譲渡特約付借地権(地主が建物を買い取ることを約束した定期借地権):30年以上
借地権は相続できる
借地権は財産的価値のある権利であり、相続財産として相続することが可能です。
借地権を相続した相続人は、被相続人と地主が交わした借地契約を承継することになり、これまでどおり借地を利用することができます。
また、借地権は現金や預貯金などと同様に相続税の課税対象となり、相続人が相続を拒否したい場合は相続放棄の手続きも可能です。
借地権の相続では、原則地主の許可は不要
借地権を相続する場合、基本的に地主の許可は不要です。
相続手続きをおこなう中で、相続によって借地権を取得したことを知らせる程度で問題ありません。
たとえ被相続人と同居していなくても借地権は相続可能で、土地の賃貸借契約書を書き換える必要もありません。
具体的な手続きの進め方については「借地権の相続手続きの流れ」で後述します。
借地権の相続で地主の許可が必要なケース
基本的に借地権の相続では地主の許可は不要ですが、例外的に以下のようなケースでは許可が必要です。
法定相続人以外の人が遺贈を受ける場合

法定相続人とは、民法で定められた相続権を有する人のことを指します。
上図のとおり相続では優先順位があり、「被相続人の配偶者」と「最も相続順位の高い人」が法定相続人となります。
遺贈とは、被相続人の遺言で第三者に遺産を譲ることを指します。
たとえば、被相続人の遺言書に「友人Aに借地権を譲る」などと書かれていた場合は、地主の許可を得る必要があります。
相続した借地権を売却する場合
相続した借地権は売却することもできます。
しかし、売却するためには地主の許可が必要で、無断で売却した場合は契約違反として借地契約を解除される可能性があります。
相続後に増改築・建替えをする場合
多くの場合、借地契約では「増改築禁止特約」が設けられており、増改築などをするためには地主の許可が必要です。
地主の承諾を得ずにおこなってしまうと、契約違反として借地契約を解除される可能性があります。
借地権の相続手続きの流れ
相続手続きをおこなう際は、基本的に以下のような流れで対応します。
- 不動産の全部事項証明書を取得する
- 名義変更に必要な書類を集める
- 地主に連絡する
- 法務局にて名義変更の申請をする
- 相続税の申告をおこなう
ここでは、各手続きについて解説します。
1.不動産の全部事項証明書を取得する
まずは、法務局にて借地権の対象となる不動産の全部事項証明書を取得します。
全部事項証明書には不動産の所在や登記記録などが全て記載されており、法務局窓口・郵送・オンラインにて請求できます。
2.名義変更に必要な書類を集める
名義変更のためには以下のような書類が必要で、市区町村役場で取得できます。
- 相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 借地権を相続する人の住民票
- 固定資産評価証明書
- 登記申請書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書または遺言書 など
3.地主に連絡する
地主の許可が不要なケースでも、何の連絡もせずに相続したことを知らせないままでいると、のちのちトラブルに発展することもあります。
今後も良好な関係性を維持していくためにも、借地人の相続によって借地権を取得したことを伝えましょう。
4.法務局にて名義変更の申請をする
準備した書類を法務局に提出し、名義変更の手続きをおこないます。
なお、その際は以下のような登録免許税がかかります。
- 建物所有権の名義変更にかかる登録免許税:固定資産税評価額×0.4%
- 借地権の名義変更にかかる登録免許税:固定資産税評価額×0.2%
5.相続税の申告をおこなう
借地権も相続税の課税対象となるため、相続税の申告が必要です。
相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です(相続税法第27条)。
期限を過ぎてしまうと延滞税や無申告加算税などのペナルティが課されるため、必ず期限内に手続きを済ませましょう。
借地権の相続で地主の許可が必要な場合の手続き
借地権の相続で地主の許可が必要なケースでは、以下のように対応します。
地主に連絡して承諾料を支払う
地主の許可が必要な場合、地主に連絡して借地権について話し合いをおこない、承諾料を支払って承諾してもらうというのが基本的な流れです。
承諾料はケースによって異なり、目安としては以下のとおりです。
|
相続状況
|
承諾料の目安
|
|
法定相続人以外の人が遺贈を受ける場合
|
借地権価格の10%程度
|
|
相続した借地権を売却する場合
|
借地権価格の10%程度
|
|
相続後に増改築・建替えをする場合
|
更地価格の3%~5%程度
|
地主が承諾してくれない場合は裁判所に申立てをおこなう
地主とのやり取りが難航して許可を得るのが難しい場合は、裁判に移行します。
家庭裁判所にて「地主の承諾に代わる許可」を求める申立てをおこない、裁判手続きを経て認められた場合は遺贈・売却・増改築・建替えなどが可能となります。
ただし、交渉や裁判などの経験がない素人では適切に対応するのは困難です。
弁護士なら問題解決に向けた具体的なアドバイスが望めますので、なかなか地主が承諾してくれない場合や、裁判を検討している場合は一度相談してみましょう。
借地権の相続で相続税申告する際の評価方法
相続税の申告をする際は、借地権の種類によって評価方法が異なります。
ここでは、借地権ごとの評価方法を解説します。
普通借地権の場合
普通借地権の場合、以下の式で計算します。
- 普通借地権の相続税評価額=土地の評価額×借地権割合
※土地の評価額:路線価方式または倍率方式で算出
※借地権割合:地域によって異なる
路線価・倍率・借地権割合については「国税庁ホームページ」で確認できます。
計算方法については、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。
定期借地権の場合
定期借地権の場合、以下のような式で計算します。
- 定期借地権の相続税評価額=土地の評価額×定期借地権割合×逓減率
定期借地権の場合は計算方法が複雑で、定期借地権割合と逓減率はそれぞれ以下のような式で求めます。
- 定期借地権割合=定期借地権等の設定時における借主の所有となる経済的利益の総額÷定期借地権等の設定時におけるその宅地の通常の取引価格
- 逓減率=課税時期における定期借地権等の残存期間年数に応じた基準年利率による福利年金原価率÷定期借地権等の設定期間に応じた基準年利率による複利年金現価率
なお、上記の基準年利率や複利年金現価率に関しては、国税庁ホームページの「令和6年分の基準年利率について(法令解釈通達)」で確認できます。
一時使用目的の借地権の場合
一時使用目的の借地権に関しては、雑種地賃借権の評価方法が適用されます。
評価方法は2種類あり、「地上権に準ずる権利として評価するのが相当」と認められる場合は以下のような式で計算します。
- 一時使用目的の借地権の相続税評価額=雑種地の自用地としての価格×法定地上権割合と借地権割合のいずれか低いほうの割合
一方、上記以外の場合は以下のような式で計算します。
- 一時使用目的の借地権の相続税評価額=雑種地の自用地としての価額×法定地上権割合×1/2
借地権の相続でよくあるトラブルと対処法
ここでは、借地権の相続でよくあるトラブルと対処法について解説します。
子ども名義で借地に建物を新築・増改築する
「親の借地上にある建物を取り壊し、子ども名義で二世帯住宅を建てようとして地主と揉める」というのはよくあるトラブルのひとつです。
このようなケースでは地主の許可が必要で、無断でおこなうと契約違反として借地契約を解除される可能性があります。
建物を建て替えたい場合は、まず地主に連絡して「建物の建て替え」と「借地権の譲渡・転貸」について承諾してもらいましょう。
地主から地代の値上げを要求されている
地主のなかには、常に地代の値上げの機会をうかがっていて、相続をきっかけに値上げを要求してくることもあります。
借地権を相続しても契約条件自体は変わらないため、基本的に地代の値上げに応じる必要はありません。
ただし、今後の関係性などを考えて、少額の値上げであれば応じるという選択肢もあります。
弁護士なら「値上げの金額が妥当かどうか」「応じるべきか拒否するべきか」などのアドバイスが望めますので、対応に困った際は相談してみましょう。
地主が亡くなった・新しい地主に変わった
地主が死亡した場合は、借地権の相続と同様に地主の相続人が借地契約上の貸主の地位を相続することになります。
これまでの権利義務関係の全ては相続人に継承されるため、借地権は影響を受けず、契約内容も変わりません。
地代の支払い先に関しても、基本的には相続人が伝えてくれるため、連絡が来るのを待ちましょう。
借地権の相続に関するよくある質問
ここでは、借地権の相続に関するよくある質問について解説します。
借地権の相続放棄は可能?
借地権を相続したくない場合、相続放棄することも可能です。
ただし、相続財産の一部だけを相続放棄することはできないため、借地権だけでなくプラスの財産もマイナスの財産も全て放棄することになります。
契約期間中でも借地契約は解約できる?
原則として、借地権の契約は中途解約できません。
ただし、解約したい旨を地主に伝えることで応じてもらえる可能性はあるため、解約したい場合は地主に連絡してみましょう。
さいごに|借地権の相続で困ったら弁護士に相談を
借地権を相続する場合、名義変更や相続税申告などのさまざまな手続きが必要で、なかには地主とトラブルになったりすることもあります。
「なかなか地主が承諾してくれない」「地代の値上げを要求されている」など、借地権のトラブルで悩んでいる場合は弁護士に相談しましょう。
弁護士ならトラブル解決に向けた的確なアドバイスが望めるうえ、依頼者の代理人として手続きを代行してもらうことも可能です。
当サイト「ベンナビ相続」では、相続に強い全国の法律事務所を掲載しており、初回相談無料の事務所も多くあるので、まずは一度相談してみましょう。