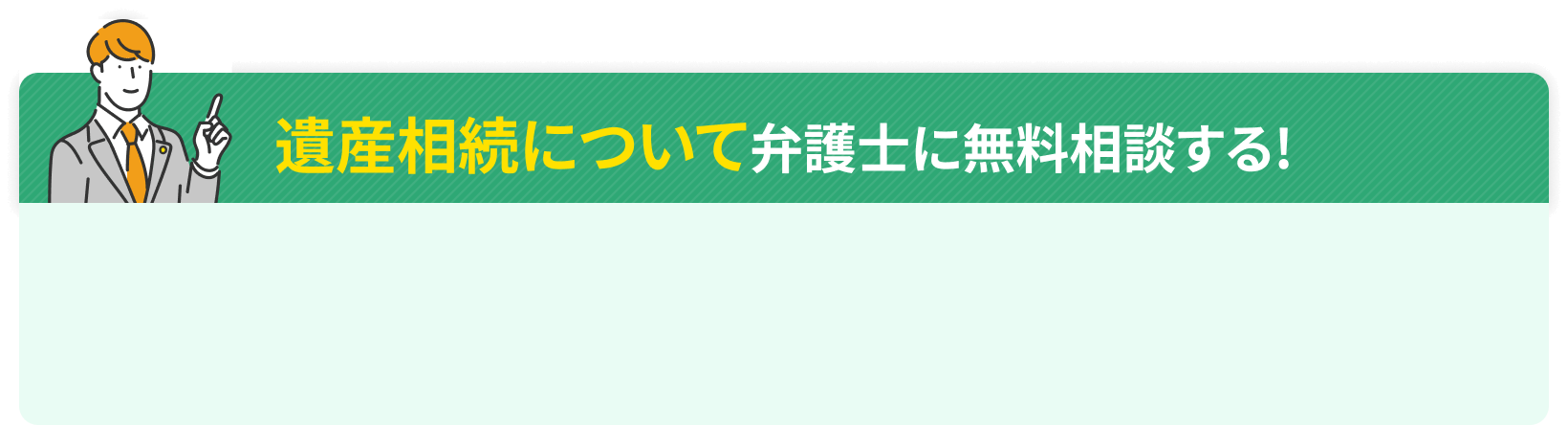遺言書の作成は自分でおこなうこともできますが、素人ではどのように書けばよいか迷ってしまったり、作成方法を誤って効力が無効になってしまったりするおそれもあります。
不備なくスムーズに遺言書を作成したい場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。
しかし、なかには「具体的にどのようなメリットがあるのか」「弁護士に依頼したくても弁護士費用が気になる」「司法書士や行政書士とは何が違うのか」などが気になっている方も多いでしょう。
本記事では、遺言書作成を弁護士に依頼するメリットや弁護士費用の相場、弁護士に依頼する際の流れや、司法書士や行政書士との違いなどを解説します。
遺言書に関する悩みや問題を抱えている方は、弁護士に相談・依頼することをおすすめします
弁護士のサポートを得ることで、以下のようなメリットが望めます。
- 遺言どおりに遺産分割がスムーズに進む
- 遺言者の希望を踏まえつつ、必要な事項を正確に記載した遺言書を作成できる
- 遺言書の内容について相続人同士での争いが生じにくくなる
- 遺言書の内容について事前に紛争リスクをチェックしてもらえる など
当サイト「ベンナビ相続」は、遺言者作成などの相続手続が得意な全国の弁護士を掲載しています。
電話や面談などでの初回相談を無料にしている法律事務所もあります。
まずは以下から近くの弁護士を探して相談してみましょう。
遺言書を作成するなら弁護士に依頼するのがおすすめ
遺言書を作成する大きな目的は、遺言者の希望を実現すること、そして相続トラブルを防ぐことです。
弁護士なら、法的視点から適切な形式で遺言書を作成してくれるだけでなく、相続人同士でトラブルが発生した場合には解決のサポートもしてくれます。
特に相続で避けたいのは、遺言者の意思が相続人に正確に伝わらなかったり、形式不備などで遺言が執行されなかったりすることです。
もし相続トラブルに発展した場合には、家族間での争いによって関係性に亀裂が走ってしまう可能性もあります。
思うような形で相続が実現しなかったり、家族がバラバラになったりするような事態を避けるためにも、遺言書を作成する際は弁護士にサポートしてもらいましょう。
弁護士費用はかかるものの、トラブルなく納得のいく相続を実現するためには必要な出費だといえます。
遺言書の作成を弁護士に依頼するメリット
ここでは、弁護士に遺言書作成を依頼することでどのようなメリットがあるのかを解説します。
1.遺言書が無効になるリスクを避けられる
弁護士に依頼すれば、不備なく適切な形式で遺言書を作成してくれます。
たとえば、自筆証書遺言を作成する場合には、以下のような法律上の要件を満たしている必要があります。
- 遺言者本人が全文を自筆で書く
- 作成した日付を自筆で書く
- 氏名を自筆で書く
- 遺言書に押印する
- 訂正箇所には取り消し線を引いて押印する など
弁護士に依頼すれば、上記の要件を満たした遺言書を確実に作成してくれるため、形式上の不備で無効になることは基本的に考えられません。
また、自分がどのような相続を望むのかを弁護士に伝えれば、弁護士はそれを文字に起こして遺言書を作成してくれます。
2.最適な遺言方法を選ぶことができる
弁護士に依頼することで、最適な遺言方法を決定できるというのもメリットです。
遺言書は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類あります。
それぞれメリット・デメリットがあり、どの遺言書が向いているのかは状況によって異なりますが、弁護士なら最適な遺言方法をアドバイスしてくれます。
遺言書の種類
| |
作成者 |
作成後の保管場所 |
開封時の検認手続 |
| 自筆証書遺言 |
遺言者本人 |
自宅または法務局 |
必要
(法務局で保管した場合は不要) |
| 公正証書遺言 |
公証役場の公証人 |
公証役場 |
不要 |
| 秘密証書遺言 |
遺言者本人 |
自宅 |
必要 |
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が自分で書いて作成する遺言書のことです。
遺言書の中でも手軽に作成できるのが大きな特徴ですが、作成後に遺言者が自分で保管していた場合、相続人が開封する際は家庭裁判所での検認手続が必要です。
また、自筆証書遺言の場合は偽造や紛失の可能性があるほか、保管場所を相続人全員に明確に伝えておかないと遺言書が発見されないおそれもあります。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場にて公証人が作成する遺言書のことです。
公正証書遺言の場合、遺言者が公証役場に行き、証人2名立ち合いの下、公証人が遺言内容を聞き取って遺言書を作成します。
作成後は公証役場に保管されるため偽造や紛失などの心配はありませんが、自筆証書遺言に比べると作成に手間や費用がかかるというデメリットもあります。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言内容を秘密にしたまま遺言書の存在のみを公正役場で証明してもらう、というタイプの遺言書です。
秘密証書遺言の場合、遺言者が自分で遺言書を作成して封や押印をしたのち、公証役場に持参し、遺言者の申述や日付の記入・署名・押印をおこないます。
遺言内容を誰にも知られずに済むのが大きな特徴ですが、作成後は遺言者が自分で保管しなければならず、内容の不備に気付かずに作成手続を進めてしまって無効になることもあります。
3.相続財産を正確に調査してくれる
遺言書に財産の分け方を記載する場合、「どのような財産があるのか」「その財産にどれだけの価値があるのか」などを正確に調べて把握しておく必要があります。
ただし、相続財産調査では各所に連絡して書類を取り寄せたりする必要があり、全て自力で対応しようとすると手間も時間もかかります。
弁護士は相続財産調査にも対応できるほか、財産の内訳をまとめた財産目録の作成や、分割の難しい不動産などの相続方法に関するアドバイスも望めます。
4.相続トラブルの予防・解決が望める
遺言書作成は司法書士や行政書士などにも依頼できますが、弁護士であれば法的なトラブルにも対応してもらうことが可能です。
弁護士は法律問題を扱う専門家であり、「どのような文言を遺言書に入れればよいか」「どのように書けばトラブルを防止できるのか」など、状況に応じて適切な内容を遺言書に入れてくれます。
遺言書作成後に相続人同士でトラブルが起きてしまったとしても、弁護士なら司法書士や行政書士とは違って調停や訴訟に制限なく対応でき、スムーズな問題解決が望めます。
5.遺言執行などの相続手続も一任できる
弁護士は、遺言書作成・遺言書の保管・遺言執行・死後のトラブル対応など、相続手続の大部分に対応しています。
弁護士の法律知識やノウハウにより、遺言書だけでなくさまざまな相続手続の進行や問題解決がスムーズにできるというのもメリットのひとつです。
遺言書作成後は遺言内容を確実に実行することが大切ですが、弁護士なら遺言執行者として、各金融機関での手続きや遺産分配などの必要な手続きを代行してくれます。
弁護士に遺言執行を依頼する主なメリットとしては以下のとおりで、遺言内容の実現に向けて的確なサポートが望めます。
- 法律知識や経験を活かして滞りなく遺言執行の各手続きを実施できる
- 相続人間で不満が生じても説得力のある対応が期待できる
- 煩雑な事務作業から解放されて相続人の負担を軽減できる
- 遺言書の内容を確実に実行して故人の希望を叶えられる
遺言書作成にかかる弁護士費用の相場
ここでは、遺言書の作成や遺言執行などを依頼した場合の弁護士費用について解説します。
なお、弁護士費用は法律事務所によってもバラつきがあるため、必ずしも以下の範囲内に収まるとはかぎりません。
正確な金額を知りたい方は直接法律事務所に確認しましょう。
| 依頼内容 |
費用相場 |
| 法律相談 |
1時間あたり5,000円~1万円程度
(初回相談無料の法律事務所もあります) |
| 遺言書の作成 |
10万円~30万円程度 |
| 遺言書の保管 |
1万円程度 |
| 遺言の執行 |
約30万円~ |
相談料|1時間あたり5,000円~1万円程度
弁護士に遺言書作成を依頼したい場合、まずは法律相談をおこなうのが通常です。
弁護士との法律相談では時間ごとに相談料が発生し、1時間あたり5,000円~1万円程度が一般的な相場です。
ただし、法律事務所によっては初回相談無料のところもあります。
また、相談方法としては面談・電話・メール・LINE・オンラインなどがあり、どれに対応しているかは事務所によっても異なります。
遺言書の作成費用|10万円~30万円程度
遺言書の作成費用の相場は、10万円~30万円程度です。
ただし、必ずしも上記の範囲内に収まるとはかぎらず、遺言内容や財産状況などによっても変動します。
たとえば、記載内容が複雑な場合や遺産の金額が大きい場合などは、100万円以上の費用がかかることもあります。
遺言書の保管費用|1万円程度
遺言書の作成後は安全な場所に保管しておく必要がありますが、弁護士に保管を依頼することも可能です。
弁護士に依頼する場合は保管費用がかかり、年間1万円程度が一般的な相場です。
自分で保管する場合と弁護士に保管を依頼する場合の主なメリット・デメリットをまとめると、以下のとおりです。
| |
メリット |
デメリット |
| 自分で保管する場合 |
・保管費用がかからない
・いつでも取り出し可能 |
・紛失・盗難・火災などのリスクがある
・遺言者が亡くなった場合、相続人が遺言書を発見できない可能性がある |
| 弁護士に保管してもらう場合 |
・安全に保管される
・遺言者が亡くなった場合、相続人へ確実に通知される |
・年間1万円程度の保管費用がかかる
・取り出すためには法律事務所へ行く必要がある |
もし自宅で保管する場合は、耐火性のある金庫に保管するなど、紛失・盗難・火災などのリスクをできる限り減らすための対策が必要です。
弁護士に保管を依頼する場合は、法律事務所で保管してもらうのが一般的で、費用はかかりますが安全に保管しておきたい場合はおすすめです。
遺言執行の費用|約30万円~
弁護士に遺言執行を依頼する場合も費用が発生します。
弁護士費用は遺言執行の業務内容や遺産の規模などによっても異なりますが、一般的な内容であれば約30万円~が相場です。
遺言執行を依頼する場合、弁護士が主に担当する業務は以下のとおりです。
- 遺言書に基づく遺産の分配
- 財産目録の作成
- 預貯金の払戻手続
- 不動産の登記手続
- 受贈者の対応
- 電気・ガス・水道・携帯電話・通信契約などの解除手続
- 証券口座の払戻手続
- 葬儀・埋葬の申込み
- そのほか、遺言者が契約で指示した手続き など
遺産金額ごとの執行費用の目安としては以下のとおりです。
| 遺産金額 |
費用相場 |
| 300万円以下の場合 |
30万円程度 |
| 300万円を超え1,000万円以下の場合 |
30万円~70万円程度 |
| 1,000万円を超え3,000万円以下の場合 |
70万円~100万円程度 |
| 3,000万円を超える場合 |
100万円以上 |
弁護士に遺言書作成を依頼する際の流れ
ここでは、遺言書の作成を弁護士に依頼する場合の一般的な流れについて解説します。
- 弁護士を探す
- 法律相談で遺言書作成のアドバイスを受ける
- 弁護士に遺言書作成を依頼する
- 希望する場合は遺言書完成後のサポートを受ける
1.弁護士を探す
まずはインターネットなどで弁護士を探して、相談予約を取りましょう。
なお、弁護士を探す際の注意点として「どの分野を得意しているか」「これまでどのような案件に対応してきたのか」をよく確認しましょう。
一口に弁護士といっても、それぞれ得意分野や解決実績などが異なり、対応経験の浅い弁護士を選んでしまうと的確なサポートが受けられないおそれがあります。
弁護士を探すのが負担に感じる方には、当社の弁護士ポータルサイト「ベンナビ相続」がおすすめです。
ベンナビ相続では、遺言書作成などの相続手続が得意な全国の弁護士を掲載しています。
相談内容や地域を選択するだけで一括検索でき、弁護士との相談が初めての方でも自分に合った相談先を効率的に探すことができます。
2.法律相談で遺言書作成のアドバイスを受ける
弁護士との法律相談では、家族構成や希望内容についてヒアリングをおこなったのち、遺言書の作成方法や遺言内容などの具体的なアドバイスを受けます。
自筆証書遺言にするのか、それとも公正証書遺言にするのかなど、弁護士のアドバイスを受けながら自分に合った形式を選択しましょう。
なお、遺言書作成では以下のような書類が必要となりますが、遺言内容によっても必要となる書類は異なるため、詳しくは弁護士に相談しましょう。
| 遺言者の本人確認ができる資料 |
運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・健康保険証・住民票・印鑑証明書など |
| 遺言者と相続人との続柄がわかる書類 |
住民票・戸籍謄本など |
| 財産関係書類 |
預貯金の通帳・不動産の登記簿謄本・株式の株券・車の車検証・貴金属の証明書など |
3.弁護士に遺言書作成を依頼する
法律相談後、弁護士に遺言書作成を依頼する場合は契約を結びます。
遺言書は3種類ありますが、なかでも自筆証書遺言や公正証書遺言が利用されることが多く、以下ではそれぞれの作成の流れを解説します。
自筆証書遺言の作成を依頼する場合
自筆証書遺言の場合、基本的に弁護士が原案を作成してくれます。
原案の内容が自分の意図と異なっている可能性もあるため、弁護士に任せきりにせずにしっかり確認し、訂正が必要なときはしっかりと伝えましょう。
遺言者本人が了承したら、遺言書の執筆作業に移ります。
下書きをもとに遺言者本人が全文を自筆で書き、もし間違いがあれば弁護士から指摘が入ります。
執筆が終わったら弁護士と遺言者本人が内容を確認し、問題なければ自筆証書遺言の完成となります。
作成後は弁護士に保管を依頼することも可能ですが、自筆証書遺言書保管制度を利用して法務局に預かってもらうことも可能です。
公正証書遺言の作成を依頼する場合
公正証書遺言の場合も、原案は弁護士が作成するのが一般的です。
遺言者本人が原案を確認して問題なければ、弁護士が公証役場と連絡を取り、原案や資料を送って作成日の日程調整をおこないます。
作成日当日は、遺言者本人・証人2名・弁護士が公証役場に出向き、公証人が準備している公正証書遺言の内容を確認します。
なお、同行する弁護士に証人になってもらうことも可能です。
問題なく手続きが進み、署名押印すれば公正証書遺言の完成となります。
公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、遺言者本人は謄本を受け取ることになります。
4.希望する場合は遺言書完成後のサポートを受ける
遺言書の保管や遺言執行などの手続きも依頼する場合は、遺言書完成後も引き続きサポートを受けることになります。
遺言書の保管を依頼した場合は、状況確認のために定期的に弁護士から連絡を受けて、もし意向が変わった場合は遺言書を作り直すことも可能です。
遺言執行を依頼した場合は、遺言者の死亡後に遺産分配や遺言者が指示した手続きなどに対応してくれます。
遺言書作成に関する弁護士とほかの専門家の違い
遺言書作成に関する相談先としては、弁護士のほかに司法書士や行政書士などがあります。
弁護士・司法書士・行政書士の主な違いをまとめると、以下のとおりです。
| |
弁護士 |
司法書士 |
行政書士 |
| 特徴 |
法律・裁判の専門家 |
法律事務・登記手続きの専門家 |
役所手続き・書類作成の専門家 |
| 遺言書作成のサポート範囲 |
◎
法的リスクも考慮した、オーダーメイドでの適切な遺言書を作成してくれる |
〇
法的に有効な遺言書を作成してくれる |
△
ヒアリングに基づいて、有効な形式の遺言書を作成してくれる |
| 相続トラブルの対応 |
〇 |
△
(認定司法書士の場合、140万円以下の案件なら対応できる) |
× |
| 依頼費用 |
△
比較的高額になりやすい |
〇
弁護士よりも安く済む可能性がある |
◎
最も安く済む可能性がある |
| おすすめのケース |
・相続トラブルに発展するおそれがある
・将来の相続トラブルを予防したい
・相続財産の種類が多い
・相続関係が複雑である |
・相続財産の中に不動産が含まれる
・相続トラブルの不安がない
・依頼費用を抑えたい |
・相続財産の種類が少ない
・相続人が少ない
・相続トラブルの不安がない
・できるだけ依頼費用を抑えたい |
弁護士と司法書士の違い
司法書士とは、法律・司法に関する手続きをおこなう専門家であり、遺産相続では主に相続登記や必要書類の作成などに対応しています。
弁護士と同様に遺言書作成を依頼することは可能ですが、弁護士との大きな違いとして相続トラブルの解決を依頼することはできません。
例外的に法務大臣の認定を受けた認定司法書士であれば対応可能ですが、認定司法書士でも140万円以下の案件しか対応できません。
司法書士の場合は上記のような制限があるため、相続トラブルが不安な場合は弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士と行政書士の違い
行政書士は、官公署への提出書類の作成や手続きの代行をおこなう専門家であり、遺産相続では主に遺言書や遺産分割協議書などの書類作成に対応しています。
司法書士と同様、行政書士も相続トラブルの解決を依頼することができません。
なお、行政書士に遺言書作成を依頼した場合の費用相場は10万円~20万円程度で、弁護士や司法書士に依頼するよりも安く済むこともあります。
ただし、依頼先事務所によっても金額にはバラつきがあるため、必ずしも安く済むとは限りませんし、依頼後に思わぬ形で相続トラブルが発生して弁護士が必要になることもあります。
相続トラブルが不安な場合や、状況に適した遺言書を作成してもらいたい場合は、弁護士に依頼しておくことをおすすめします。
遺言書の作成を弁護士に依頼する際の注意点
ここでは、遺言書の作成を弁護士に依頼する際の注意点について解説します。
遺言書作成後もサポートしてくれる弁護士を選ぶこと
「遺言書を作成するなら弁護士に依頼するのがおすすめ」でも触れたとおり、遺言書作成の主な目的は、遺言者の希望を実現すること、そして相続トラブルを防ぐことです。
遺言書作成を依頼する際は、作成後も引き続きサポートしてくれる弁護士を選ぶことが大切です。
これまで大きなトラブルもなく家族間の仲が良好だったとしても、実際に相続が発生するとお互いの取り分などで揉めて関係性が悪化してしまうこともあります。
すぐに頼れる弁護士がいないと、揉め事がどんどん大きくなり、当事者同士では解決困難な状況になって裁判に発展する可能性もあります。
できるだけ穏便な形で相続を済ませるためにも、遺言書作成だけでなく相続発生後の対応も依頼できる弁護士を選んだほうが安心です。
相続トラブルが不安な場合は最初から弁護士に依頼すること
司法書士や行政書士は、遺産相続手続の一部を代行することはできますが、法的紛争の解決には対応できません。
相続トラブルを未然に防ぎ、円滑な遺産分割を実現するためにも、相続トラブルが不安な場合は最初から弁護士に依頼することを検討しましょう。
特に以下のようなケースではトラブルに発展するおそれがあるため、最初から弁護士に依頼することをおすすめします。
- 相続人になる人が複数いる場合
- 家族関係が複雑な場合
- 評価の難しい遺産がある場合
- 親族同士で過去の遺恨や金銭トラブルがある場合 など
さいごに|遺言書作成が得意な弁護士を探すなら、ベンナビ相続がおすすめ
トラブルなく確実に相続を済ませたいのであれば、弁護士に遺言書作成を依頼することをおすすめします。
弁護士なら、不備なく適切な形式で遺言書を作成してくれるだけでなく、遺言執行や相続トラブルの解決などの遺言書完成後もサポートを受けることができます。
ベンナビ相続なら、相談内容や地域を選択するだけで遺言書作成が得意な弁護士を効率的に探せますので、弁護士への相談・依頼を考えている方はぜひご利用ください。
初回相談無料の法律事務所も多く掲載しているので、弁護士費用が気になる方もまずは一度相談してみましょう。