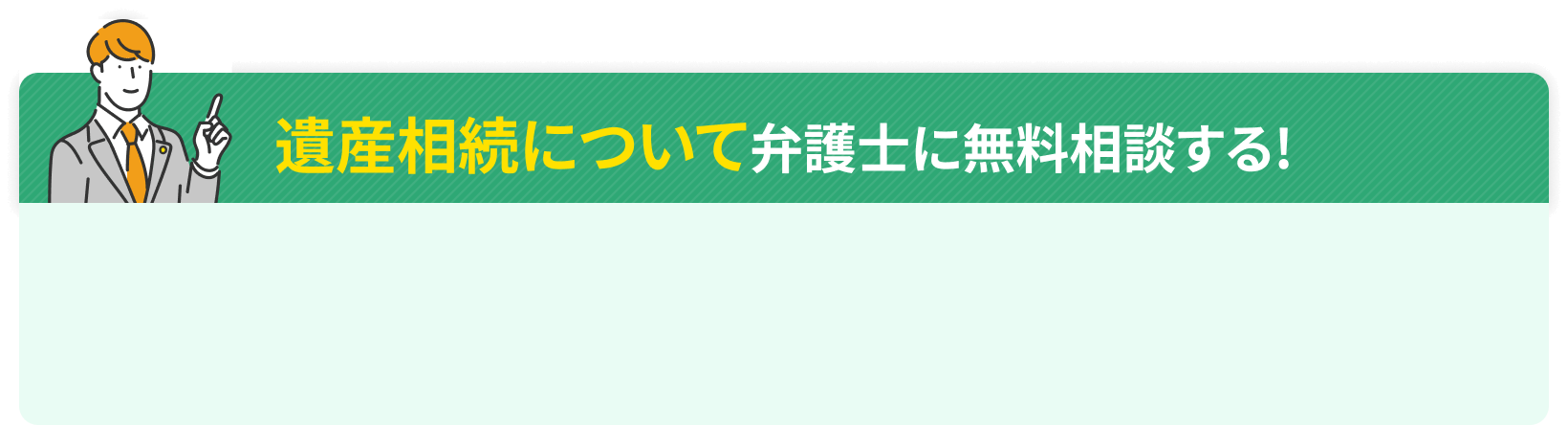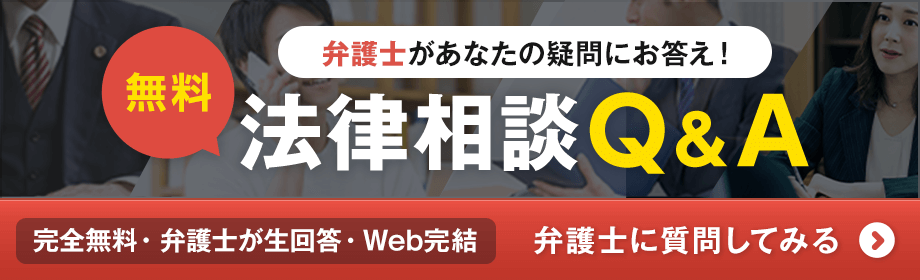被相続人が生前に仕事などを通して、小説の出版・写真や絵画の発表・生活雑貨や建築物のデザインを行っていれば、被相続人はそれらの著作権を所有していることになります。
著作権は申請をせずとも、創作した時点で付与されるものです。この著作権は、被相続人が亡くなると相続財産となり、相続することが可能です。
では、著作権にはどのような権利が含まれており、相続はどのように行えばいいのでしょうか?
著作権が相続財産になるかわからないあなたへ
著作権が相続財産になるかわからず悩んでいませんか?
結論から言うと、著作権は相続財産になります。
著作権の相続について不安な場合、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
弁護士に相談することで以下のようなメリットを得ることができます。
- 著作権の相続人を決めるアドバイスがもらえる
- 依頼すれば、遺産分割協議書に著作権を記載するのを任せられる
当サイトでは、著作権の相続をはじめとする相続問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。
この記事に記載の情報は2025年01月16日時点のものです
まずは著作権に含まれる権利についてご紹介します。
著作権とは
一般的に使われる「著作権」という言葉には、何らかの表現を経て著作者の思想的感情を盛り込んだ著作物を支配する権利が含まれています。代表的なもので言えば、知的財産権などですね。
知的財産権(ちてきざいさんけん、Intellectual property)とは、有体物(動産と不動産)に対して認められる所有権とは異なり、無体物(情報)を客体として与えられる財産権のことである。 知的所有権(ちてきしょゆうけん)とも呼ばれる。
参考:Wikipedia
著作権がある著作物として代表的なものは、音楽・小説・映画・写真・コンピュータープログラム・建築物・美術品などです。著作権は、大きく2種類の権利に分かれています。その権利は、「著作者人格権」と「著作権(財産権)」です。
著作者人格権とは、著作者が制作した著作物に関わる人格的な利益を保護することを目的とする権利の総称です。つまり、著作者人格権の中には様々な権利が含まれているのです。
小説・映画・音楽などを代表する著作物には、著作者の考えや主張が強く反映されているため、第三者が著作物の利用方法を誤ると、著作者の人格的な利益や本来伝えたいことが損なわれてしまう可能性があります。
このような自体を防止するために、著作者人格権が設けられています。
著作者人格権は、著作者のみが所持する権利で、譲渡や相続が不可能となっています。これを一身専属権といいます。
そのため、著作者が亡くなると一定の範囲を除いて、この権利は消滅します。
財産権とは
財産権は、特許権などと同様の知的財産権のひとつです。この財産としての意味合いが強い著作権は、著作物の全てまたはその一部を譲渡や相続することが可能です。
譲渡や相続を行った場合の著作権の権利者は、著作物を制作した著作者本人ではなく、著作権を新しく取得した人となるため注意が必要です。
例えば、すでに亡くなった著作者の小説が文庫本や全集となり出版される場合、その売上で発生した印税は著作権を現在所有している人が受け取る権利を持ち、自動的に相続人等に配当されるというわけではありません。
著作権に含まれるもの
著作者人格権と著作権(財産権)には、いくつかの権利が含まれています。その権利を整理しておきます。
著作人格権
|
氏名表示権
|
自分の著作物を公表するときに、著作者名の表示の有無、表示する場合は実名か変名かを選択できる権利
|
|
公表権
|
自分の著作権の中で、未公表のものを公表するかどうか、公表する場合はいつ・どのように公表するかを決められる権利
|
|
同一性保持権
|
自分の著作物の内容やタイトルは自分の医師に反して勝手に変更されない権利
|
財産権
|
複製権
|
著作物を印刷・複写・録音・録画・写真などの方法で別の形に再製する権利
|
|
上演権・演奏権
|
著作物を公に上演・演奏する権利
|
|
上映権
|
著作物を公に上映する権利
|
|
公衆送信権・伝達権
|
著作物を公衆からアクセスできるようにすること(自動公衆送信)や、放送・有線放送などをする権利
|
|
口述権
|
言語による著作物を朗読などによって口頭で公に伝える権利
|
|
展示権
|
美術品などの著作物と未発表の写真著作物の現作品を公に展示する権利
|
|
頒布(はんぷ)権
|
映画の著作物の複製品を販売・貸し出す権利
|
|
譲渡権
|
映画以外の著作物の原作または複製品を公衆へ譲渡する権利
|
|
貸与権
|
映画以外の著作物の複製物を公衆へ貸し出す権利
|
|
翻訳権・翻案権
|
著作物を翻訳・変形・編曲・編集などする権利。二次的著作物を制作することに対する権利
|
|
二次的著作物の利用権
|
自分の著作物を原作とする二次的著作物を利用することに対し、二次的著作物の著作権者と同様の権利
|
相続は原則的に、被相続人の相続財産に属した全ての権利と義務を承継します。しかし、被相続人の一身に専属したものはこの承継に含まれないとされています。
つまり、一身に専属したものは相続の対象にならないということです。一身に専属したものとは、相続人が承継することが適当でないと判断される権利を指します。この権利の代表的なものは、生活保護受給権や身元保証人としての地位などです。
「・著作者人格権とは」で述べたように、著作人格権は一身に専属したもの(一身専属権)とされているため、相続の対象となりません。対象となるのは著作権(財産権)のみです。
この著作権(財産権)を相続する場合には、著作権の移転手続きをする必要はありません。相続人の間で話し合いを行い、著作権(財産権)を相続する人を決めましょう。
ただし、複数の相続人が分割して著作権を相続するようなケースでは、文化庁に「著作権・著作隣接権の移転等の登録手続き」を申請することになります。
詳しくは文化庁のホームページをご覧ください。
著作権(財産権)の移転手続きが必要ない理由は、小説・音楽・映画・写真などの著作物は、これらが制作された時点で、自動的に著作権が発生しているからです。そのため、基本的には著作物の著作権を取得する手続きはありません。
よって、著作権(財産権)の相続でも特別な手続きは必要ないため、相続人を合意の上で決めることだけに注力しましょう。
相続人同士の話し合いで決められる著作権(財産権)の相続は、簡単なように思えますが意外な落とし穴がある場合があります。口約束だけで著作権(財産権)の相続を行い、後になって権利などの問題でトラブルが発生する可能性があるからです。
そのため、遺産分割協議書を作成することをオススメします。書面として著作権(財産権)の相続の内容が記録されていれば安心です。
著作権には存続期間(原則的保護期間)が設けられています。その存続期間は、著作者が著作物を創作してから著作者の死後50年間までです。著作者が変名・無名または団体名義の場合は公表後50年間が存続期間となります。
ただし、映画の著作物の場合のみ公表後70年間が存続期間となります。
著作権(財産権)以外にも相続財産となるものがあります。意外と見落としがちな権利であるため、知っておくと良いでしょう。
被相続人が技術者や工業製品の開発を仕事にしていた場合、「特許権」「実用新案権」「工業所有権」などの権利を所有している可能性があります。特許権と実用新案権は、著作人格権のような一身専属権ではないため、相続の対象となります。
これらは著作権(財産権)と同様で、権利の移転手続きは必要ありません。しかし、工業所有権のみ、相続したことを特許庁長官に対して届け出る必要があるため注意しましょう。
今回の記事でご紹介した著作権についての知識は、自分自身が著作者でなければなかなか知らないことではないかと思います。もし被相続人が著作権を所有しているのであれば、相続人がその権利を承継します。
相続には特に手続きがいらないとはいえ、自身がどのような権利を相続したのか知っておくことは重要なことです。今回の記事があなたの著作権相続への理解の手助けとなれば幸いです。
[bengo_promtext_end]