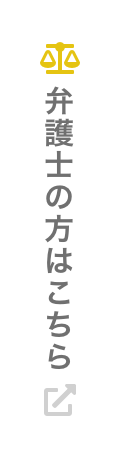遺産分割に関する弁護士相談をご検討中の方へ
遺産分割に関する弁護士相談をご検討中の方へ
遺産分割協議は法的に明確な期限が定められていません。
しかし、特定受益や寄与分の主張期限を考えると、実質的に10年間という期限があると考えられます。
特別受益や寄与分の主張については、令和3年の民法改正によって期間制限が設けられました。
しかし、どのような変化があったか詳しく理解できていないという方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、遺産分割協議の期限が10年とされる理由について解説します。
あわせて特別受益や寄与分の主張期限についても解説するのでぜひ参考にしてください。
遺産分割協議の期限は法律上定められていません。
しかし、実質的な期限は10年といわれることが多くあります。
以下ではその理由について解説していきます。
遺産分割は、被相続人が亡くなったあと、いつどのタイミングからでも開始することが可能です。
遺産分割をおこなわないままだと、相続遺産の所有者がはっきりしない状態が続くことになります。
とくに不動産の場合は、利用したい人がいても購入できなかったり、適切な管理がおこなわれず放置されたりといった問題が生じます。
そのため、遺産分割協議の期限は定められていないものの、なるべく早いタイミングでおこなうことが推奨されます。
遺産分割協議をなるべく早くおこなうよう促すために、令和3年の民法改正にて、遺産分割協議における特別受益および寄与分の主張をできる期限が10年となりました。
特別受益とは、相続人の一部のみが被相続人から生前贈与・遺贈・死因贈与などで受け取った利益のことを指します。
一部の相続人のみが受け取った利益があると、相続人間で不平不満が生まれトラブルに発展することが考えられます。
そこで、得た利益を特別受益として遺産分割時に加味して計算することで、各相続人が相続する遺産の偏りを軽減することができます。
寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人に対して、法定相続分よりも多く財産を相続できるようにする制度です。
特別な貢献の例としては、被相続人の家業を無給で手伝っていた、長期にわたって被相続人の介護に専念していたなどのケースがあげられ、以下の要件を満たす必要があります。
令和3年の民法改正(令和5年4月1日施行)では、この特別受益と寄与分の主張ができる期限が設定されました。
この改正により、相続開始から10年が経過すると原則として特別受益や寄与分の主張ができなくなります。
特別受益や寄与分があったのにもかかわらず、10年の期限を超過してしまった場合は、それらが主張できなくなります。
結果として法定相続分もしくは指定相続分で遺産分割をおこなうことになるため、場合によって本来得られるはずだった財産より少なく分割される可能性があります。
法定相続分とは、遺産相続において法律上定められた遺産分割の割合のことを指します。
具体的には被相続人との関係性をもって以下のように定められています。
また、一方で指定相続分とは遺言によって指定された相続分のことを指します。
相続開始から10年を過ぎてしまったとしても、例外として相続人全員の合意が得られれば、特別受益や寄与分を加味した遺産分割をおこなうことが可能です。
ただし、相続人によっては特別受益や寄与分を認めることで受け取れる遺産が少なくなることから、合意を得られない可能性が高くなるでしょう。
このような事態を防ぐためには、相続開始から10年以内に家庭裁判所へ遺産分割請求をおこない、特別受益や寄与分の主張を行う必要があります。
なお、特別受益や寄与分の主張に関する民法改正は経過措置が設けられています。
経過措置が適用されるケースと経過措置の内容は以下のとおりです。
民法改正施行時にすでに相続の開始から10年が経過している場合は、民法改正施行時から5年以内まで特別受益および寄与分の主張が可能です。
民法の改正施行前に相続が開始しており、改正施行時から5年以内に10年が経過してしまう場合は、同じく法改正施行時から5年以内まで特別受益および寄与分の主張が可能です。
たとえば、民法改正施行時に相続の開始からすでに7年が経過しており、あと3年で主張期限を迎えてしまう場合でも、民法改正施行時から5年以内、つまり相続の開始から12年経過するタイミングまで主張が認められます。
遺産分割協議が長期間おこなわれず、相続遺産が放置されたままになってしまうことは少なくありませんでした。
しかし、相続開始から長期間が経過すると、証拠が散逸するなどして他の相続人が反証等をすることが困難になってしまいます。
このような点を考慮し、遺産分割協議を特別受益や寄与分の主張により多くの財産を取得できると考える相続人に対し、一定期間内に必要な手続をとらせることとしました。
遺産分割が未了のまま放置されている不動産等が社会問題になりつつある中で、早期の遺産分割協議を促す狙いもあるといえるでしょう。
このような改正の趣旨に照らしても、特別受益や寄与分を主張したいと考えている方は早期に専門家に相談し、手続きをとった方が良いといえるでしょう。
特別受益や寄与分以外にも、遺産相続に関連した手続きにおける期限が複数存在します。
ここではそのなかでも、円滑に遺産分割をすすめるにあたって特に知っておくべき代表的な期限をみていきましょう。
相続放棄の期限は、相続の開始から3ヵ月以内です。
相続放棄とは、借金などマイナスの財産を含め遺産を相続する権利を放棄する手続きを指します。
相続財産に多くの負債が含まれる場合など、相続放棄を検討すべきケースは少なくありません。
相続放棄をする場合は、期限に遅れないように手続きをすすめることが必要です。
相続税の申告および納税の期限は相続の開始から10ヵ月以内です。
それまでに遺産分割協議をおこなっていない場合は、一旦法定相続分で相続したと仮定して、相続税を納める必要があります。
この期限までに遺産分割協議をおこなうことが必須ではありませんが、相続税を低くする特例は適用できません。
あとから申告をし直すことで還付を受けることは可能ですが、手間が増えたり申告時の相続税が高くなったりするデメリットがあります。
民法改正によって不動産を相続し所有権を取得した場合は、3年以内に名義変更をする(相続登記をおこなう)ことが義務付けられました。
相続登記を期限以内におこなわなかった場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があるので注意しましょう。
なお、遺産分割協議が3年以内にまとまらなかった場合は、法定相続分で相続したことにして相続登記をおこない、その後改めて登記をしなおすことも可能です。
ただし、その分、登記の手間や費用が増えることになるため、なるべく3年以内に遺産分割協議をおこなうことが推奨されます。
遺産分割協議を後回しにした結果、特別受益や寄与分の主張がおこなえず、本来得られるはずの相続財産を得られなくなったり、税制上損をしてしまったりする可能性があるため注意しましょう。
遺産分割協議について悩みがある場合は、専門家である弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に相談することで状況にあわせた最適な選択肢を提案してくれ、スムーズに進めることが可能になります。
法律事務所によっては無料相談をおこなっているところもあるので、まずは相談してみるところからはじめてみましょう。
遺産分割協議には明確な期限がないものの、令和3年の民法改正により特別受益と寄与分の主張に関する期限が定められ、実質的な期限が10年といわれるようになりました。
また、それ以外にも相続放棄や相続税の期限などを加味すると、遺産分割協議はなるべく早くおこなってしまうのが得策といえます。
相続に関する問題は状況に合わせた最適な選択肢を取る必要があり、一般の人からはハードルが高い課題に感じてしまうこともあるかもしれません。
そこで法律の専門家である弁護士に相談することで、スムーズな解決が期待できます。
本記事や弁護士からのアドバイスを参考に、遺産分割協議を速やかに進めていきましょう。
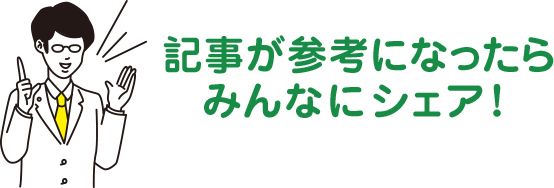

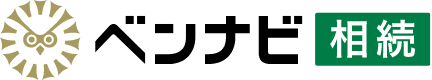
遺産相続では相続人ごとに優先順位が定められており、相続人の組み合わせによってそれぞれの取り分が異なります。本記事では、相続順位・相続割合のルールや、パターンごと...
遺産相続にあたって遺産分割協議書をどのように作成すればよいのか、悩んで方も多いのではないでしょうか。本記事では、遺産分割協議書の必要性や具体的な書き方を解説しま...
遺産相続で兄弟姉妹の意見が対立してしまいトラブルになってしまうケースは少なくありません。民法には、遺産相続の割合や順位が定められているので、原則としてこの規定に...
法定相続人の順位が高いほど、受け取れる遺産割合は多いです。ただ順位の高い人がいない場合は、順位の低いでも遺産を受け取れます。あなたの順位・相続できる遺産の割合を...
遺産相続を依頼した際にかかる弁護士費用の内訳は、一般的に相談料・着手金・成功報酬金の3つです。相続の弁護士費用がいくらかかるのかは、どんな解決を望むかで異なりま...
養子縁組を結んだ養親と養子には、法律上の親子関係が生じます。養子には実子と同じく遺産の相続権が与えられるうえに、相続税の節税にもつながります。このコラムでは、養...
特定の相続人に遺産を相続させない方法を知りたくはありませんか?夫・妻・兄弟はもちろん、前妻の子・離婚した子供に財産・遺留分を渡したくない人は注目。悩み解消の手助...
株式の相続が発生すると、株式の調査や遺産分割、評価や名義の変更などさまざまな手続きが必要になります。この記事では、株式の相続で必要な手続きについて詳しく解説しま...
遺産分割協議とは、相続人全員による遺産分割の話し合いです。この記事では、遺産分割協議の進め方や、不動産など分割が難しい財産の分配方法などを解説するとともに、話し...
法定相続分とは、被相続人(亡くなった人)が遺言で財産の配分を指定しなかった場合に適用される「遺産の相続割合」のことです。本記事では、法定相続分の配分や計算方法を...
配偶者居住権は、2020年4月より適用されるようになった権利をいいます。本記事では、配偶者居住権の概要や設定の要件、メリット・デメリットなどを解説します。手続き...
一人が全て相続するケースでも、状況によっては遺産分割協議書が必要になることがあります。 本記事では、遺産を一人が全て相続する際の遺産分割協議書の書き方や注意点...
本記事では、遺産分割協議の期限が10年とされる理由について解説します。あわせて特別受益や寄与分の主張期限についても解説するのでぜひ参考にしてください。
本来、同居と別居だけでは遺産相続に関するルールに変更が生じることはありませんが、被相続人が同居人に有利な遺言書を遺すこともあるため、同居人とそれ以外の相続人の間...
遺言書についてトラブルを抱えている場合、まずは弁護士と相談するのがおすすめです。遺言書の無効を主張したり、遺留分侵害額請求を申し立てなければならない可能性もあり...
本記事では、相続におけるお金の渡し方を知りたい方に向けて、相続のお金の渡し方に関する基礎知識、生前と死後それぞれのお金を渡す方法、お金の渡し方について相談できる...
本記事では、遺産相続の連絡がない状況を放置するデメリットや連絡なしの状態に追い込まれたときの対処法を解説します。ベンナビ相続では、遺産相続問題に強い弁護士を多数...
不当利得返還請求とは、不当に利益をもらっている人から得した分のお金などを返してもらうように請求することです。本記事では、相続で損したお金を返してもらうための請求...
親の財産を兄弟姉妹で遺産相続する場合、トラブルが起きやすいので要注意です。 本記事では、兄弟姉妹が遺産相続で争ったときの解決策や、公平に遺産分割する方法などを...
遺産相続にあたって、兄弟姉妹間で不平等が生じていることに対し、不満を抱いている方も多いのではないでしょうか。本記事では、不公平な相続があった場合の対処法をケース...