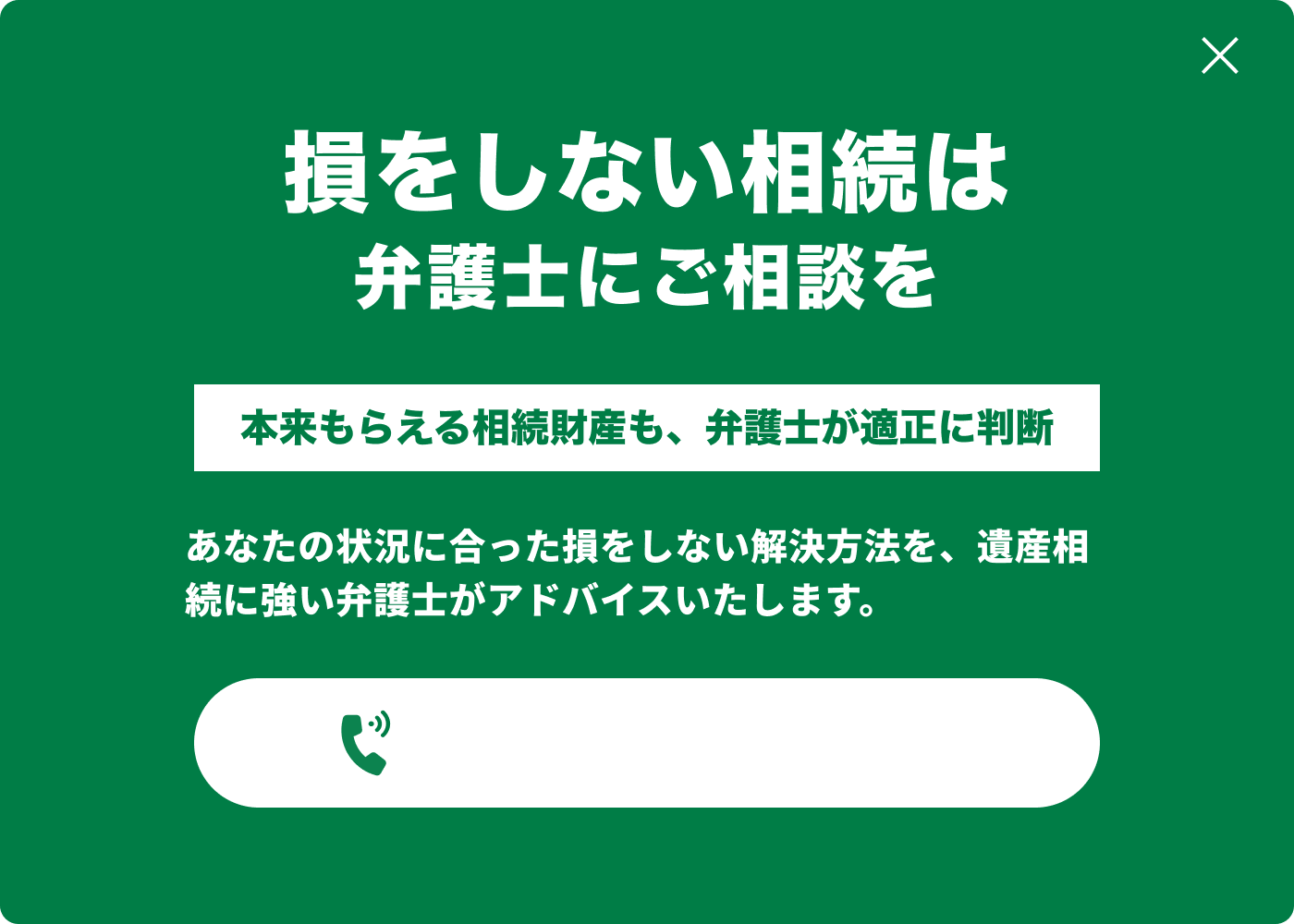相続税に関する弁護士相談をご検討中の方へ
相続税に関する弁護士相談をご検討中の方へ
相続した遺産に対しては相続税が課されますが、基礎控除額に達するまでは非課税となります。
また、基礎控除のほかにも、相続税の負担を軽減できる特例や控除が設けられています。
各種の特例や控除をうまく活用して、相続税の負担を軽減しましょう。
本記事では、相続税はいくらまで無税なのか、子どもの人数に応じた基礎控除額の計算方法などを解説します。
相続などによって取得した財産には、相続税がかかるのが原則です。
ただし、基礎控除額に達するまでの財産は非課税とされています。
基礎控除額は、法定相続人の数に応じて計算します。
相続税の「基礎控除」とは、一定の額に達するまでの相続財産などについて、相続税を非課税とする制度です。
基礎控除の最低額は3,000万円で、法定相続人の数が多ければ多いほど増えます。
相続税の基礎控除額は、以下の式によって計算します。
法定相続人の最低人数は0人なので、相続税の基礎控除の最低額は3,000万円となります(法定相続人が0人でも、生前贈与や遺贈によって財産を取得した人に対して相続税が課されることがあります)。
一方、相続税の基礎控除額に理論上の上限はありません。
「法定相続人」とは、民法によって遺産を相続する権利があるとされている人をいいます。
以下の順位に従い、最上位の人だけが法定相続人となります(民法887条1項、889条1項)。
※上記のほか、配偶者は必ず法定相続人になります(民法890条)。
※直系尊属の中では、被相続人と親等の近い者が上位となります(例:父母の方が祖父母よりも優先)。
なお、被相続人の子または兄弟姉妹が死亡・相続欠格・相続廃除のいずれかによって相続権を失った場合は、その人の子が代襲相続によって法定相続人となります(民法887条2項、889条2項)。
また、被相続人の孫以降の直系卑属が死亡・相続欠格・相続廃除のいずれかによって相続権を失った場合は、その人の子による再代襲相続も認められています(民法887条3項)。
下記、例となります。
相続税の基礎控除額は、原則として法定相続人1人当たり600万円増えます。
ただし養子については、被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までしか法定相続人としてカウントできません。
下記、例となります。
なお、相続放棄をした人は初めから相続人にならなかったものとみなされますが(民法939条)、相続税の基礎控除との関係では法定相続人としてカウントできます。
下記、例となります。
これに対して、相続欠格または相続廃除によって相続権を失った人は、相続税の基礎控除との関係でも法定相続人としてカウントすることができません。
下記、例となります。
被相続人の子どもの人数と、配偶者の有無に応じた相続税の基礎控除額は、下表のとおりです。
|
配偶者なし |
配偶者あり |
|
|
子ども0人 |
代襲相続人、または第2順位以降の法定相続人の数による ※最低3,000万円 |
代襲相続人、または第2順位以降の法定相続人の数による ※最低3,600万円 |
|
子ども1人 |
3,600万円 |
4,200万円 |
|
子ども2人 |
4,200万円 |
4,800万円 |
|
子ども3人 |
4,800万円 |
5,400万円 |
|
子ども4人 |
5,400万円 |
6,000万円 |
|
子ども5人 |
6,000万円 |
6,600万円 |
|
子ども6人 |
6,600万円 |
7,200万円 |
|
子ども7人 |
7,200万円 |
7,800万円 |
|
子ども8人 |
7,800万円 |
8,400万円 |
|
子ども9人 |
8,400万円 |
9,000万円 |
|
子ども10人 |
9,000万円 |
9,600万円 |
※養子は、実子がいる場合は1人のみ、実子がいない場合は2人までカウントできます。
相続税の課税対象となるのは、以下の財産です。
被相続人の遺産(=相続財産)以外にも、相続税が課される財産があるので、見落とさないように注意しましょう。
被相続人が死亡時に所有していた財産(遺贈または死因贈与がなされたものを除く)は、法定相続人が相続する「相続財産」に当たります。
相続財産は、相続税の課税対象とされています(相続税法1条の3第1項第1号~第4号)。
遺言によって贈与された財産は、相続税の課税対象とされています(相続税法1条の3第1項第1号~第4号)。
また、贈与者が死亡したことを停止条件として効力を生ずる贈与を「死因贈与」といいます。
死因贈与によって被相続人から取得した財産も、相続税の課税対象です(同)。
被相続人の死亡によって取得する点で相続財産と類似していること、相続税の課税逃れを防止する必要があることなどを理由に、法律上の相続財産ではない一部の財産が相続税の課税対象とされています。
このような財産を「みなし相続財産」といいます。
みなし相続財産に当たる主な財産は、以下のとおりです(相続税法3条、4条)。
相続開始(=被相続人の死亡)の時期に応じて、下表の期間に受けた贈与の額は、相続税の課税価格に加算されます(=贈与財産の加算、相続税法19条)。
|
相続開始の時期 |
加算対象期間 |
|
~2026年12月31日 |
相続開始前3年以内 |
|
2027年1月1日~2030年12月31日 |
2024年1月1日から死亡の日までの間 |
|
2031年1月1日~ |
相続開始前7年以内 |
暦年課税の基礎控除(年110万円)を利用して無税で贈与した財産も、上記の加算対象期間に贈与がおこなわれた場合は、相続税の課税対象になるので注意が必要です。
なお、売買などにより対価を支払って被相続人から取得した財産は、原則として贈与財産の加算の対象外です。
ただし、著しく低額の対価によって被相続人から財産を譲り受けた場合は、対価と時価の差額に当たる贈与がなされたものとみなされ、贈与財産の加算の対象になることがあります(相続税法7条)。
60歳以上の直系尊属(父母や祖父母など)から、18歳以上の人が贈与を受ける場合は「相続時精算課税」を選択することができます(相続税法21条の9)。
贈与税は、1年間に受けた贈与の額に対して、毎年課税されるのが原則です(=暦年課税)。
しかし、相続時精算課税を選択すると、通算2,500万円に達するまでは贈与税が非課税となります。
その反面、相続時精算課税が適用される贈与は、基礎控除額(年110万円)を除いた部分全額が相続税の課税対象となります。
なお、いったん相続時精算課税を選択すると、それ以降同じ人から受ける贈与について常に相続時精算課税が適用されます。
暦年課税に戻すことはできないのでご注意ください。
下記、例となります。
一部の財産は、上記のルールによって課税対象となる場合でも、相続税が非課税とされています(相続税法12条)。
主な相続税の非課税財産は、以下のとおりです。
相続または遺贈によって財産を取得する相続人または受遺者が負担する以下の債務のうち、確実と認められるものは、相続税の課税価格から控除することができます(相続税法13条、14条)。
過大な相続税が課されることを防ぐため、債務控除は漏れなく集計しましょう。
相続税の負担を軽減するには、以下の方法などを活用して、相続税の課税対象となる財産を減らすことが効果的になることがあります。
家庭や財産の状況に応じて、適切な方法により相続税対策を講じましょう。
贈与税には、毎年110万円の基礎控除が設けられています。
基礎控除の範囲内であれば、無税で財産を贈与することが可能です。
贈与税の非課税枠を利用して、毎年少しずつ家族などへ生前贈与をすると、最終的に残る相続財産が減るため、相続税の負担を軽減することができます(=暦年贈与)。
ただし暦年課税の場合は、基礎控除を利用した無税の贈与であっても、加算対象期間(=前掲、相続開始前3~7年以内)におこなわれたものには相続税が課されてしまいます(=贈与財産の加算)。
相続税の負担を効果的に軽減したいなら、早い段階から暦年贈与を始めましょう。
なお相続時精算課税が適用される贈与については、基礎控除(年110万円)の範囲内であれば、時期にかかわらず相続税が課されません。
贈与財産の加算を避けたいときは、相続時精算課税を選択することも有力な方法の一つです。
基礎控除額(年110万円)を超える部分の贈与額に対しては、贈与税が課されるのが原則です。
ただし以下の非課税特例を利用すると、資金の使途は限定されますが、基礎控除額を超える贈与も一定額まで非課税となります。
直系尊属から家屋の新築・取得・増改築等に要する費用の贈与を受けた場合、省エネ等住宅については1,000万円まで、それ以外の住宅については500万円まで贈与税が非課税となります。
30歳未満の人が、金融機関を通じて直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合、1,500万円まで贈与税が非課税となります。
18歳以上50歳未満の人が、金融機関を通じて直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合、1,000万円まで贈与税が非課税となります。
上記の各非課税特例は上限額が高いため、まとまった額の相続財産を一挙に減らすことができます。
ただし、教育資金または結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合において、期間中に贈与者が死亡したときは、残った金額について相続税が課されることがあるので注意が必要です。
手元に現金や預貯金があるときは、その資金で不動産を購入すると、相続財産の評価額を減らせることがあります。
不動産の相続税評価額は、土地については路線価方式または倍率方式によって計算し、建物については固定資産税評価額となります。
土地・建物のいずれについても、相続税評価額は購入価格よりも低く抑えられるケースが多いです。
結果的に、不動産の購入によって相続財産の評価額が減少し、相続税の負担が軽減される可能性があります。
また、被相続人と生計を同一にする親族が事業用または居住用に使用する宅地等を購入すると、相続発生後にその宅地等について「小規模宅地等の特例」の適用を受けられることがあります。
小規模宅地等の特例を利用すると、宅地等の相続税評価額が最大80%減額され、相続税の負担を大幅に軽減できます。
生命保険契約に基づく死亡保険金には、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が設けられています。
法定相続人の数のカウント方法は、相続税の基礎控除と同じです。
手元に現金や預貯金がある場合は、その資金を一括払いするなどして生命保険に加入すると、相続税の課税価格を減らすことができます。
相続財産などの総額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告・納付をしなければなりません。
相続税が課される場合でも、以下の特例や控除を効果的に利用すれば、相続税の負担を軽減できることがあります。
利用できる特例や控除を見逃さず、漏れなく利用しましょう。
被相続人の配偶者が取得した課税対象財産については、「配偶者の税額の軽減」を適用することができます。
配偶者の税額の軽減を利用すると、配偶者が取得した課税対象財産のうち、以下のいずれか多い金額に相当する相続税が軽減されます。
相続または遺贈によって財産を取得した時に18歳未満であった法定相続人は、相続税の額から以下の金額を差し引くことができます(=未成年者の税額控除)。
※1年未満の期間があるときは、切り上げて1年として計算します。
下記、例となります。
なお、未成年者本人の相続税額よりも未成年者控除額が大きいため控除しきれない場合は、その未成年者の扶養義務者の相続税額から控除することができます。
ただし、過去の相続において未成年者控除を受けたことがある場合は、すでに受けた控除額が未成年者控除額から差し引かれます。
相続または遺贈によって財産を取得した時に85歳未満の障害者であった法定相続人は、相続税の額から以下の金額を差し引くことができます(=障害者の税額控除)。
下記、例となります。
なお、障害者本人の相続税額よりも障害者控除額が大きいため控除しきれない場合は、その障害者の扶養義務者の相続税額から控除することができます。
ただし、過去の相続において障害者控除を受けたことがある場合は、すでに受けた控除額が障害者控除額から差し引かれます。
相続税の課税価格に加算された贈与財産について、すでに贈与税を納付している場合は、贈与税額を相続税額から控除することができます(=贈与税額控除)。
ただし、加算税・延滞税・利子税は相続税額から控除することができません。
相続開始前3~7年以内に受けた贈与や、相続時精算課税が適用される贈与については、贈与税額控除を受けられることがあるので忘れずに確認しましょう。
相続開始前10年以内に、亡くなった被相続人が相続・遺贈・相続時精算課税が適用される贈与によって財産を取得して相続税が課されていた場合は、今回の相続における相続税額から一定額を差し引くことができます(=相似相続控除)。
相似相続控除額は、前回の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で減額した後の金額です。
相続税の計算方法は非常に複雑であるため、正しく計算するのは大変です。
しかし、正しい知識に基づいて生前対策や申告をおこなえば、相続税の負担を軽減できる可能性があります。
相続税の計算・申告手続き・節税対策などについては、税理士に相談しましょう。
相続税を得意とする税理士に相談すれば、家庭や財産などの状況に応じて具体的にアドバイスを受けられます。
相続税の申告や節税対策とともに、遺産分割などの相続手続きや遺言書の作成などの相続対策も併せて専門家に依頼したい場合は、税理士と連携している弁護士に相談するのが安心です。
「ベンナビ相続」には、税理士と連携のある弁護士が多数登録されているので、ぜひご活用ください。

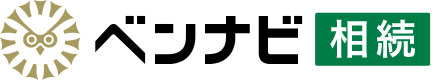
相続税の税率は10%~55%の超過累進課税で、取得金額が大きいほど高くなります。相続税の計算は複雑ですが、流れを理解すれば自分でも計算できます。本記事では、相続...
相続税には配偶者控除(配偶者の税額軽減制度)があり、配偶者が取得した相続財産のうち1億6,000万円または法定相続分相当額のどちらか高い方が控除できるというメリ...
不動産を相続する際に最も気になる相続税も、やり方次第で大きな節税を行うことができます。今回は相続税の計算方法や不動産を相続する際の注意点などをご紹介していきます...
遺産相続をすると税金がかかるのをご存知でしょうか。二次相続は一次相続と違い、配偶者控除を利用できないので多くの相続税を払う必要があります。ここでは、配偶者控除に...
ここでは相続をする人が知っておくべきことを以下の5つのポイントに沿って説明していきたいと思います。
税理士への相談料の相場と、費用が発生するタイミング、そして費用を抑えて賢く税理士を利用するためにはどうすれば良いのかをご紹介していきます。
相続税の申告手続きは、相続人自らがおこなう必要があります。しかし、相続財産の内訳や相続・遺贈の状況、法定相続人の数によって、相続税の申告手続きは異なります。本記...
相続税対策の代表例としては生前贈与が挙げられます。しかし相続や贈与にはさまざまな非課税枠が設けられており、状況に応じた適切な判断が必要となります。この記事では、...
代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)とは、代襲相続が起こった際に本来の相続人に代わって相続人になった「本来の相続人の子」などのことをいい、代襲者(だいしゅうしゃ...
一時払い終身保険は相続税対策として有効な手段のひとつですが、注意して利用しないと相続税以外の税金が課されたりする場合もあります。本記事では、一時払い終身保険を相...
相続した不動産を売却する場合、譲渡所得税などの税金が発生しますが、特例制度を利用すれば節税できます。また、不動産売却時には注意点があるので、ポイントをおさえたう...
相続税申告をする際に添付書類として提出するのが印鑑証明書です。印鑑証明書についてはほかの手続きでよく発行からの期限を定められている場合があるのですが、相続税申告...
不動産を所有していた方が亡くなり相続が発生すると、固定資産税の支払いは誰がおこなうべきなのでしょうか。誰に支払い義務があり、誰が負担するのか、未払い分があったら...
相続対策として生命保険が利用されるケースは数多くあります。しかし、具体的な活用方法を理解している人は少ないのではないでしょうか。本記事では、相続時における保険金...
相続をする際には、遺族が支払うべきものがたくさん発生します。そのため、税金の負担だけでも抑えられないのか、気になっている方も多いはずです。本記事では、相続税や所...
マンションの贈与は原則として贈与税の課税対象ですが、税金の制度は複雑なので実際にいくらかかるのか、節税できないのかなど、さまざまな疑問を抱えている方も多いはずで...
遺産が6,000万円あれば、どのくらい相続税がかかるか知っておきたいところでしょう。本記事では、遺産が6,000万円ある場合に相続税がどのくらいになるかの概算額...
税務署から届く「相続についてのお尋ね」は、税務署が相続税があるのではないかと疑っているため送ってくる書類です。本記事では、「相続についてのお尋ね」がどのような書...
家を相続するからといって、必ずしも高額な相続税が発生するとは限りません。基礎控除や特例・控除の活用によってゼロになるケースも多いです。本記事では家を相続しても相...
本記事では、親から子どもへの贈与は贈与税の課税対象になること、贈与税が課されないケースや非課税財産として扱われるケース、親子間の贈与で贈与税の負担を軽減できる非...