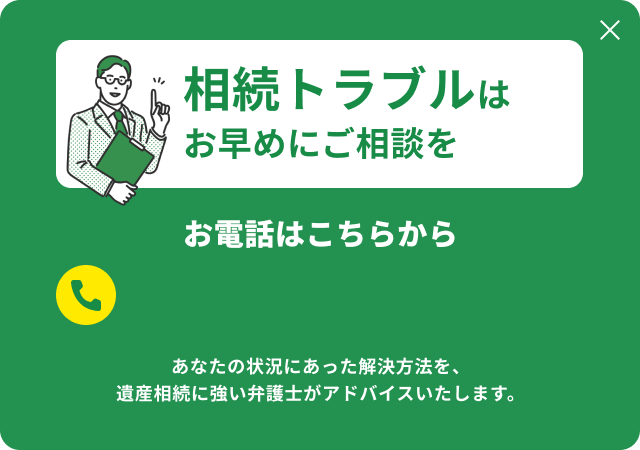事業承継に関する弁護士相談をご検討中の方へ
事業承継に関する弁護士相談をご検討中の方へ
事業承継のために会社の株式を後継者が引き継ぐ際には、相続税や贈与税が課税されます。
これらの税は、後継者が引き続き会社を経営していくにあたり、大きな負担になり得るものなので、可能な節税対策はきちんとおこなっていくのが望ましいでしょう。
この記事では、事業承継税制の概要を紹介します。
現在、税制改正に伴う特例措置が実施されているので、適用対象になりそうな企業は、積極的に活用されることをおすすめします。
|
事業承継を検討している方へ |
|
事業承継は、会社(財産)を引き継ぐ行為ですので、法的問題が絡むことが多く、トラブルも発生しやすいです。
その点、事業承継に対応できる弁護士に相談することで、
・どの事業承継方法が望ましいかが分かる ・最短でスムーズな事業承継につながる ・事業承継に関連した相続争いを防げる ・弁護士のサポートで安心して事業を引き継げる
など、多忙な経営者や後継者の様々なニーズを叶えてくれるでしょう。
まずは、無料相談などを活用してみましょう。 |
事業承継税制には、事業承継の際に生じる贈与税・相続税の負担を軽減するという税制上のメリットがあり、それにより後継者の確保にもよい影響を与えることが期待できます。
事業承継税制は、後継者である受贈者や相続人などが、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式などを、贈与や相続などによって取得した場合、その贈与や相続などにかかる税金について、一定の要件を満たし続ける限り納税を猶予し続け、その要件を満たしたまま後継者が死亡するに至った場合は、猶予されている税金の納付を免除するという制度です。
この制度を活用することにより、事業承継の際に生じる相続税・贈与税の負担を軽減することができます。
事業承継をする際に、株式を相続した相続人が相続税を納めるための資金を用意することができず、結果として事業自体の存続を断念せざるを得ないことも考えられます。
そのため、事業承継税制を設けることで、中小企業の事業承継において後継者が相続税の納税で困らないようにしています。
この税制は後継者問題の改善に役立っています。
現在の事業承継税制について、詳しく見ていきましょう。
平成30年度の税制改正により、5年以内の特例承継計画の都道府県知事への提出・確認を条件として、10年以内の贈与・相続において、一般措置では総株式数の最大3分の2までとなっていた納税猶予対象株式数の上限を撤廃し、80%であった相続による納税猶予割合を100%に引き上げる、といった特例措置が取られるようになりました。
|
特例措置 |
一般措置 |
|
|
事前の計画策定等 |
5年以内の特例承継計画の提出 |
不要 |
|
適用期限 |
10年以内の贈与・相続等 |
なし |
|
対象株数 |
全株式 |
総株式数の最大3分の2まで |
|
納税猶予割合 |
100% |
相続等: 80%、贈与:100% |
|
承継パターン |
複数の株主から最大3人の後継者 |
複数の株主から一人の後継者 |
|
雇用確保要件 |
弾力化(雇用維持ができない場合も、一定の書類を都道府県知事に提出すればよい) |
承継後5年間 |
|
事業の継続が困難な事由が生じた場合の免除 |
譲渡対価の額等に基づき再計算した猶予税額を納付し、従前の猶予税額との差額を免除 |
なし |
|
相続時精算課税の適用 |
60歳以上の贈与者から20歳以上の者への贈与 |
60歳以上の贈与者から20歳以上の推定相続人(直系卑属)・孫への贈与 |
【出典】No.4148 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等|国税庁
を加工して作成
特例措置によって、一般措置では総株式数の最大3分の2までの範囲だった納税猶予が全株式で受けられるようになったほか、納税猶予割合も相続では80%でしたが、特例措置によって贈与・相続ともに100%になりました。
以下では、相続による事業承継にあたって、特例措置を利用する場合を念頭に置いて説明します。
相続による事業承継の際に、事業承継税制の特例措置を利用するにあたっては、以下の条件をクリアしている必要があります。
ここでは簡略化して説明しますので、実際に特例措置を利用する際には、弁護士、税理士などの専門家に必ず相談するようにしてください。
先代経営者と後継者については、以下の条件があります。
特例措置は以下の会社に該当する場合は適用されません。
2023年3月31日までに、会社の後継者や承継時までの経営未投資などを記載した「特例承継計画」を策定し、税理士・商工会・商工会議所などの「認定経営革新等支援機関」の所見を記載し、都道府県知事に提出し、確認を受けることで特例措置が受けられます。
継続報告5年間の間に事業が存続していない場合、猶予税額の全額または一部、および利子税を納付しなければなりません。
ただし、やむを得ない理由がある場合には、一定部分の猶予税額が免除される場合もあります。
特例措置を受けるための「特例承継計画」の策定、都道府県知事への提出・確認をおこなったあとは、以下の手続きが必要です。
その後、相続開始から10ヵ月以内に所管の税務署に相続税の申告をおこないます。
事業承継の相談先としては、弁護士、税理士・公認会計士などが挙げられます。
ただし、それぞれが全ての相談に対応できるわけではなく、業務領域が決まっています。
自身の事業承継のフェーズに合った相談先を選ぶことが大切です。
事業承継を弁護士に依頼することで、「相続」や「M&A」などに適切に対応することができます。
「相続」による事業承継に関しては、特別受益、遺留分、遺言の有効性など、後継者への事業承継を確実に実現するうえで問題となる、様々な法的な問題があります。
また、「M&A」による事業承継についても、適正な利益を確保しつつ、事業承継を確実に実現するため、譲受事業者との条件交渉や契約条項の作成を通じて、法的な問題に適切に対処する必要があります。
事業承継を弁護士に依頼することで、「相続」や「M&A」に内在する法的リスクが実現し、紛争化してしまう前に、法的リスクに適切に対応することができます。
税理士・公認会計士は、特例承継税制の適用における税務署への書類の提出や、相続税の申告などの代行をはじめ、実際に事業承継をしたあとの税務相談にも対応することができます。
また、株式や不動産などの評価や、生前贈与対策についても税理士に相談することで、適切なアドバイスを受けることができます。
事業承継を検討されている方の中には、親族や従業員が後継者とならず、そもそも後継者候補が見当たらないということで迷われている方もいるでしょう。
そのような場合には、後継者候補を探すためのサービスを利用することも考えられます。
ビズリーチサクシードはWeb上でM&A先を探せるサービスで、広く候補者を外部に求めることができるといったメリットがあります。
事業承継には、「法律」「税金」など非常に多くの要素が絡んできます。
そのため、せっかくの特例税制を活用できなかったり、親族内で争いが起こったりすることも考えられます。
事業承継が終わらないと、新しい経営者は会社の経営どころではなくなってしまいます。
また、特例措置が適用できるのにもかかわらず適用しなかった場合、後継者が相続税や贈与税の納税に苦しみ、最悪の場合、会社をたたむといったケースに至ることも考えられます。
会社を健全に存続させ、スムーズな事業承継をおこなうためにも「弁護士」「税理士・公認会計士」などの専門家にアドバイスをもらうことが大切です。
|
事業承継を検討している方へ |
|
事業承継は、会社(財産)を引き継ぐ行為ですので、法的問題が絡むことが多く、トラブルも発生しやすいです。
その点、事業承継に対応できる弁護士に相談することで、
・どの事業承継方法が望ましいかが分かる ・最短でスムーズな事業承継につながる ・事業承継に関連した相続争いを防げる ・弁護士のサポートで安心して事業を引き継げる
など、多忙な経営者や後継者の様々なニーズを叶えてくれるでしょう。
まずは、無料相談などを活用してみましょう。 |


中小企業を経営するなかで引退を視野に入れはじめたものの、事業承継の知識がなく、行動に移せていない方も多いのではないでしょうか。本記事では、事業承継の種類や具体的...
遺産分割審の結果に不服がある場合には、高等裁判所に対して「即時抗告」の申立てが可能です。即時抗告はどのようなケースで、いつどのようにして行えば良いのでしょうか?...
土地の占有期間が長くなると、時効取得で自分の土地になる可能性があります。時効取得は所有する意思を証明する必要があり、訴訟になるケースも多いので、弁護士に協力して...
事業承継(じぎょうしょうけい)とは、会社の経営する事業を引退に伴って後継者に引き継ぐことを言い、個人事業主の場合は有形又は無形の財産、会社などは株式の全部又はそ...
今回は、事業承継に関わる相続税・消費税・税制改革など、事業承継と税金についての様々な制度をご紹介いたします。
事業承継に失敗し紛争が生じたり、会社の業績が悪化するリスクを回避するために、事業承継対策の基本的な考え方と承継の際に活用できる制度についてご紹介いたします。
この記事では、事業承継税制の概要をご紹介します。事業承継税制には、節税や後継者問題の改善などの相続対策効果があります。また現在、税制改正に伴う特例措置が実施され...
事業承継税制とは、中小企業の事業承継のうち非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除を定めた特例措置で、利用には制限があるものの、大きな節税効果を持つ...
事業承継の相談先としては、税理士などの士業や事業引継ぎ支援センターなどの公的機関があります。状況によって最適な相談先は異なるため、それぞれの特徴を確認しておきま...
事業承継を成功させ、きちんと後継者に事業を引き継ぐためには適切な事業承継計画が必要です。計画を立てる時期が遅すぎると事業承継に支障をきたす恐れがあります。この記...
本記事では、事業承継を検討している方に向けて、事業承継に関わる専門家の特徴、事業承継について相談できる窓口、専門家・相談窓口を選ぶときのポイントなどを説明します...
事業承継を実施する際には、さまざまな契約書を交わす必要があります。本記事では、事業承継の形態別に正しい契約書の記載方法を紹介します。契約書の記載方法や注意点を理...
「事業承継に興味があるが知らない人に会社を任せるのが不安」「事業承継と廃業のどちらを選ぶべきか悩ましい」と感じている人も多いのではないでしょうか?本記事では事業...
事業承継を弁護士に依頼した場合、相談料・着手金・報酬金などが発生します。本記事では、事業承継を弁護士に依頼した場合の相場や料金体系、費用面以外に確認すべきポイン...
本記事では、兄弟姉妹に会社を相続させようと考えている方に向けて、被相続人の兄弟姉妹は会社を相続できるかどうか、実の兄弟姉妹に会社を相続(承継)させる方法、遺言書...
本記事では、相続で自社株を承継させたいと考えている経営者の方に向けて、相続で自社株を承継させるメリット・デメリット、相続で自社株を承継させる際のトラブル事例、円...
本記事では、有限会社を相続しようとしている方に向けて、被相続人が有限会社を経営していた場合に相続できるもの、有限会社の株式を相続することになった際の手続きの流れ...
会社を相続する際の流れがわからず戸惑っている方もいるでしょう。本記事では、会社を相続する方法や会社を相続する際に注意すべきリスクを解説します。会社の相続について...
会社を経営していた親が亡くなった場合、会社の相続について相続をおこなう方法や具体的な手続きの流れを把握できている人は少なく、何をおこなったらよいのかわからないと...
仙台市で相続の困りごとに直面している方に向けて、無料の相続相談窓口を紹介します。市役所・区役所などの相談窓口のほか、相談時の注意点も解説するので、ぜひ相続相談の...