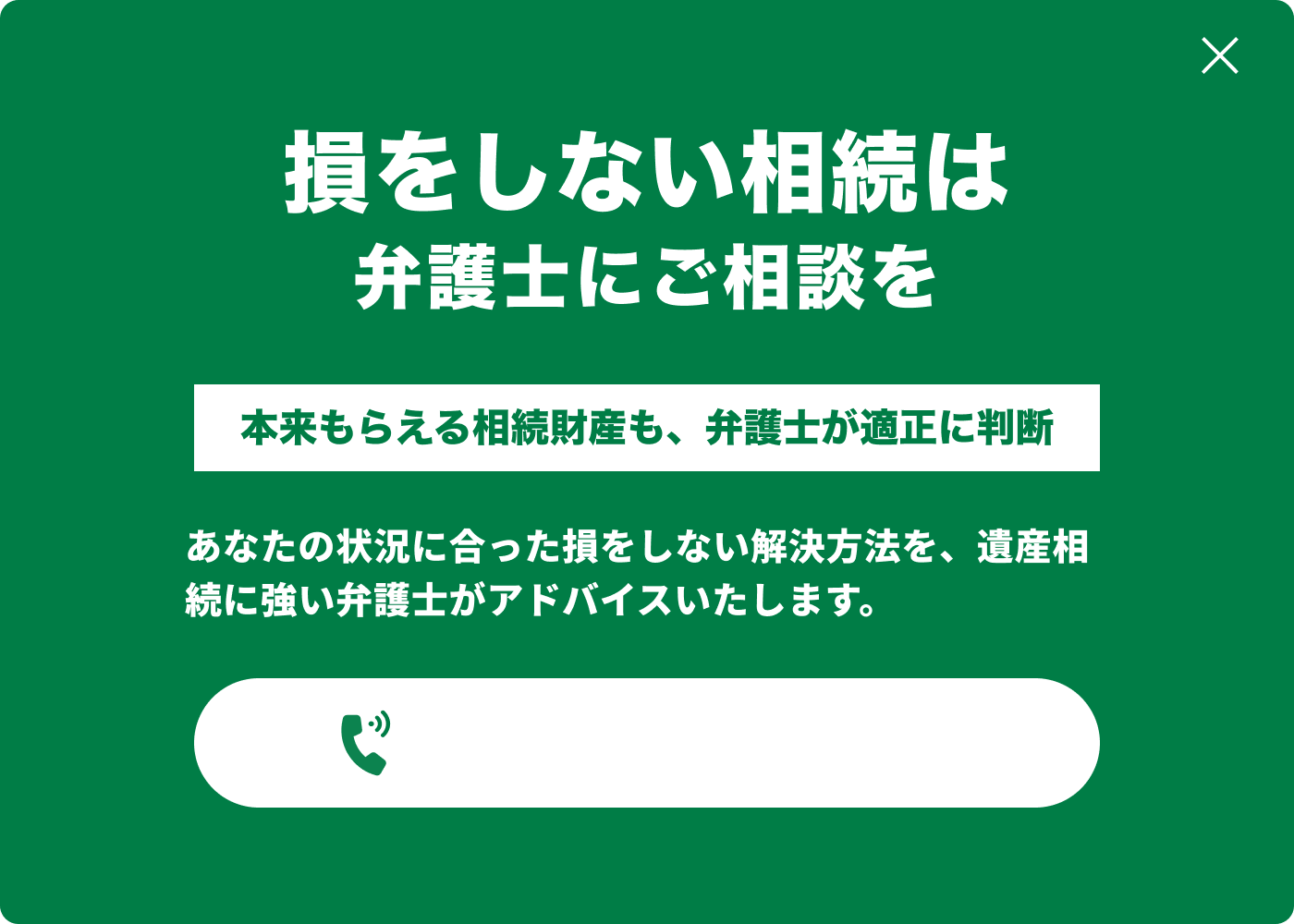2018年に民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立し、2019年から相続法が順次改正されました。
これにより現在では、配偶者居住権、特別受益の優遇措置、預貯金の払戻し、遺留分侵害額請求権などを利用することができます。
しかし、まだ創設されたばかりの新しい制度も多く、詳しく理解できていない方もいるでしょう。
そこで本記事では、2018年に成立した相続法の変更点を中心に、それぞれの制度を利用する際のポイントを解説します。
また、相続法改正と一緒に自筆証書遺言の保管制度が始まったり、相続税法や不動産登記法などの改正もおこなわれたりしています。
このような相続関連の法律の改正ポイントについても確認しましょう。
民法の相続法分野は、1980年(昭和55年)以来大きな見直しがなされることなく、平均寿命が大幅に延びて高齢化が急速に進んだ日本社会の実情に対応できていませんでした。
そこで法制度と現実社会の乖離を埋めるために、2018年(平成30年)7月に「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が成立し、相続法に関するルールが大幅に見直しされました。
主な変更点については以下のとおりです。
|
制度 |
施行日 |
概要 |
|
配偶者居住権の新設 |
2020年4月1日 |
被相続人の配偶者が、終身または一定期間、今までどおり家に住むことができる |
|
夫婦間での居住用不動産の贈与の優遇 |
2019年7月1日 |
婚姻期間20年以上の夫婦間での居住用不動産の贈与は特別受益の対象にならない |
|
預貯金の払戻し制度の新設 |
2019年7月1日 |
単独で被相続人の預貯金の一部について払戻しを受けられる |
|
自筆証書遺言の方式の緩和 |
2019年1月13日 |
自筆証書遺言の財産目録をパソコンで作成し、通帳のコピーを添付できる |
|
遺留分制度の見直し |
2019年7月1日 |
遺留分を侵害された者が、遺留分侵害額に相当する金銭を請求することができる |
|
特別の寄与の制度の新設 |
2019年7月1日 |
相続人以外の親族が無償で被相続人の療養看護などをしたとき、相続人に対して金銭を請求できる |
また、相続法の改正に伴い「法務局における遺言書の保管等に関する法律」も成立しました。
このほか相続法改正後に相続税法や不動産登記法の変更もあったため、それぞれの変更点についても解説します。
配偶者居住権とは、残された配偶者が被相続人の所有する建物に居住していた場合に、終身または一定期間、その建物に無償で居住できる権利のことです。
配偶者居住権を設定する場合は、法務局で登記をおこなう必要があります。
なお、任意の権利であるため、配偶者居住権を設定しないという選択も可能となっています。
(配偶者居住権)
第千二十八条 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
たとえば、以下のような相続のケースを考えてみましょう。
一例ですが、相続法改正前では配偶者が自宅に住み続けるためには、遺産を法定相続分で分割しなければならないため、以下のように相続する必要があります。
つまり、配偶者が今までどおりの生活を続けるためには、預貯金を諦めなければいけないということです。
相続法改正後は、建物の権利を配偶者居住権を設定することで、たとえば、「配偶者居住権(1,500万円)」「負担付き所有権(1,500万円)」に分けられます。
その結果、配偶者と子どもの相続内容を以下のようにできるようになりました。
このように配偶者居住権を設定することで、配偶者は住宅と預貯金の両方を相続できるようになったのです。
配偶者居住権は、配偶者の居住を確保するのに役立ちます。しかし、以下のようなデメリットもあります。
配偶者居住権を設定する場合は、このようなデメリットもよく検討する必要があります。
相続法の改正により、特別受益に関する優遇措置も設けられました。
これは、婚姻期間20年以上の夫婦間での居住用不動産の贈与・遺贈では、「被相続人は特別受益の規定を適用しない」と推定するルールです。
これにより不動産の贈与等が特別受益に該当しなくなり、配偶者がより多く財産を相続することができます。
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
相続法改正前は、配偶者間の自宅の贈与・遺贈などは「遺産の先渡し」として扱われました。
つまり、この不動産の贈与分は特別受益として扱われて、原則として遺産分割時にすでに取得した財産として計算されました。
たとえば、以下のようなケースを考えてみましょう。
このようなケースでは、相続の際に預貯金3,000万円を配偶者と子どもで分配するわけではありません。
生前におこなわれた建物3,000万円も相続財産に含めて、6,000万円分の相続財産を分配する必要があります。
つまり、配偶者はすでに建物3,000万円を受け取っているため、残りの預貯金3,000万円は全て子どものものとなります。
相続法改正後は、婚姻期間20年以上の夫婦間でおこなわれた居住用不動産の贈与・遺贈は、原則として、特別受益に該当しなくなりました。
その結果、贈与された分はそのまま配偶者が取得し、残りの財産を相続人同士で配分することになります。
つまり、従来のケースと異なり、以下のような相続が実現できるようになります。
夫婦間での居住用不動産の贈与等に関する優遇を利用するには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
たとえば、婚姻期間が短い、投資用不動産を贈与されたなどの場合は、同特例を利用できないため注意しなければなりません。
なお、この特例とは別に「おしどり贈与(夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除)」という贈与税の特例もあります。
夫婦間で不動産の贈与をする際は、おしどり贈与についても確認しましょう。
相続法の改正に伴い、遺産分割前でも預貯金の払戻しができる制度が新設されました。
従来から家庭裁判所の審判を経れば預貯金を引き出せる制度はありましたが、負担が大きいというデメリットがありました。
そこで遺産分割前でも預貯金の払戻しを認める制度を設け、相続人単独で一定額まで預貯金を引き出せるように改正されています。
(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
第九百九条の二 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
相続法改正前は、最高裁判所により「共同相続された預貯金は相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることなく、遺産分割の対象になる」とされていました(最高裁判所平成28年12月19日決定)。
そのため、遺産分割が終了するまでの間は、相続人が預貯金の払い戻しを受けられないという決まりになっていました。
相続法の改正により、法定相続人は以下の計算式で求められる預貯金額を単独で引き出せるようになりました。
たとえば、預金額が600万円で相続人が子ども2人の場合、1人あたり100万円(600万円×1/3×1/2)までなら自由に預貯金を引き出すことができます。
ただし、同一の金融機関から引き出しできる金額は150万円までが上限となっています。
別の金融機関なら問題ありませんが、支店が異なる場合などは合算されるため注意しましょう。
預貯金の払戻し制度を利用すると、その相続人は被相続人の財産を受け取ったと判断されます。
そのため、相続の単純承認となってしまい、相続放棄ができなくなる点には注意が必要です。
借金が財産を上回っている場合や借金額がわからない場合などで相続放棄を検討しているなら、安易に預貯金を引き出さないようにしましょう。
自筆証書遺言とは、遺言者本人が遺言書の全文を手書きで作成する遺言書のことです。
この自筆証書遺言を作成する際には、被相続人の財産をまとめた「財産目録」を添付することもできます。
従来は財産目録も手書きで作成する必要がありましたが、相続法の改正に伴いパソコンなどでの作成が認められるようになりました。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
相続法改正前では、自筆証書遺言はもちろん、財産目録も全て手書きで作成する必要がありました。
被相続人の財産が少ない場合は、手書きで財産目録を作成してもそこまで負担は大きくないでしょう。
しかし、財産の種類が多い場合には負担になります。
また、手書きの場合は書き間違いなどが生じるリスクが高いなどの懸念点もありました。
相続法の改正によって、自筆証書遺言の財産目録はパソコンで作成できることになりました。
また、通帳のコピーや登記事項証明書などを添付することも認められています。
これにより、たとえば財産目録はパソコンで作成し、遺言書に「別紙財産目録1に記載してある財産を長男に相続させる」と記載するなどの対応も簡単になりました。
手書きで作成していない財産目録などがある場合は、必ずそのページに遺言者本人による署名・押印が必要になります。
たとえば、両面印刷をしている場合は、表面・裏面のそれぞれに署名・押印が必要です。
署名・押印を忘れていると、遺言内容に納得していない相続人から「遺言が無効だ」と主張されるリスクもあるため注意しましょう。
従来、遺留分を侵害されている場合は、遺留分減殺請求による現物での返還が原則でした。
しかし、事業承継の障害になったり、不動産が共有になってしまうなどの問題がありました。
そこで遺留分制度を見直し、現物で返還する遺留分侵害額請求から、金銭で返還する遺留分侵害額請求という制度に変更されました。
(遺留分侵害額の請求)
第千四十六条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
2 遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。
一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額
二 第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額
引用元:民法 | e-Gov法令検索
相続法改正前は、遺留分を侵害されている場合に遺留分減殺請求をおこなうことができました。
この遺留分減殺請求の特徴は、現物の返還を求めるというものです。
つまり、不動産や株式などの生前贈与・遺贈がおこなわれていた場合、これらを共有することになります。
そのため、権利が複雑になってしまうなどの問題がありました。
相続法の改正によって創設された遺留分侵害請求権では、侵害額は金銭として請求できるようになりました。
そのため、従来と異なり被相続人の財産が共有状態になることを回避できます。
なお、侵害している方がすぐに金銭を用意できない場合は、家庭裁判所に申し出ることで一定期間の猶予を設けてもらえる制度も新設されています。
5 裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、第一項の規定により負担する債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
遺留分侵害額請求権は、「遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知ったときから1年以内」に行使しなければなりません(民法第1048条)。
この消滅時効を過ぎてしまうと、その後に遺留分侵害額請求がおこなえなくなります。遺留分の侵害を知ったら、早めに侵害者に対して請求をおこないましょう。
相続法の改正により、特別寄与料制度が新設されました。
特別寄与料制度とは、相続人以外の親族が被相続人の療養看護などをおこなった場合に、相続人に対して金銭を請求できる制度のことです。
特別寄与料は、相続人に対して直接請求することも可能ですし、家庭裁判所に「特別の寄与に関する処分調停」を申し立てることもできます。
第千五十条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
被相続人の長男は働いており、被相続人の介護を長男の配偶者が担当していたとします。
このような場合であっても、長男の配偶者は経済的な恩恵を得られません。
もちろん被相続人が「長男の配偶者に現金○○円を遺贈させる」という遺言書がある場合は別ですが、そうでなければ法律上、配偶者は報酬を請求できないという課題がありました。
相続法の改正によって、「被相続人以外の親族が、無償で療養看護などの労務を提供した場合」に相続人に対して貢献度に応じた金銭(特別寄与料)を請求できるようになりました。
たとえば、配偶者が介護をしていた場合、介護サービスを使わずに済んだという貢献があります。
この貢献に応じた金銭を相続人に対して請求することができます。
特別寄与料制度の創設により、長男の配偶者なども報酬を受け取れるようになりました。
しかし、配偶者が特別寄与料を請求することに対し、抵抗する相続人もいます。
また、請求するにあたり、貢献度に応じた金額を正確に計算し、その根拠も提示する必要があります。
寄与分も特別寄与料も、特別な寄与があったことを証明しなければならないため、認められるのは簡単ではありません。
ここでは、相続法の改正とともに知っておくべき相続関連の法律・制度の変更点について確認しましょう。
相続法の改正と一緒に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立したことで、法務局で自筆証書遺言を保管できるようになりました。
保管制度は遺言者自身が法務局に来庁し、事前に作成した遺言書と申請書、添付書面を提出することで利用できます。
また、相続開始後には相続人は遺言書情報証明書を法務局から交付してもらえます。
令和5年度税制改正によって、相続税法と租税特別措置法の一部が改正されました。
これにより相続税・贈与税の税制に以下のような変更点が生じています。
従来は暦年課税制度のみ、年110万円の基礎控除額が設けられていました。
しかし、2024年1月1日以降からは相続時精算課税制度でも基礎控除額が適用されます。
なお、制度自体は変わらないため相続時精算課税制度を選択すれば、2,500万円まで贈与税の非課税枠(相続時に持ち戻す必要はある)を利用することができます。
従来の生前贈与の持ち戻し期間は、相続開始前3年以内でした。
それが2024年1月1日からは相続開始前7年以内に延長されます。ただし、2024年から段階的に始まるため、いきなり7年に延びるわけではありません。
また、延長された4年間(4年前~7年前の部分)に贈与された財産は、総額100万円までは持ち戻しの加算対象外となります。
従来は、不動産を相続しても登記する義務はありませんでした。
しかし、2024年4月1日からは、相続による所有権の取得または遺産分割の成立から3年以内に相続登記をおこなう必要があります。
正当な理由がないのに相続登記をおこなわなかった場合には、10万円以下の過料が科される可能性があるので注意しましょう。
2018年7月に改正相続法が成立したことで、遺言や相続などの負担を軽減できるようになりました。
配偶者居住権や遺留分侵害額請求権、特別寄与料制度、自筆証書遺言の補完制度などさまざまな権利や制度が創設されたため、自分たちの相続に必要な手続きを確認して利用すると良いでしょう。
しかし、遺言・相続の負担が軽くなったとはいえ、ひとりで対応するのが難しい手続きも多くあります。
そのため、必要に応じて相続問題が得意な弁護士に相談するのもおすすめです。
相続問題が得意な弁護士は「ベンナビ相続」で見つけられます。
無料相談に応じている弁護士も掲載しているため、まずは弁護士を探して相談してみましょう。

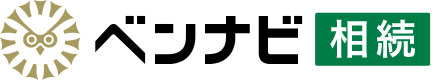
遺族年金とは、国民年金や厚生年金などの加入者が亡くなった際に支給される年金です。遺族年金は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類あり、それぞれ受給内容が異な...
除籍謄本とは、結婚や死亡などで誰もいなくなった状態の戸籍の写しのことです。除籍謄本の取得方法はいくつかあり、場合によっては除籍謄本が不要なケースもあります。この...
遺産相続とは、被相続人が残した財産・権利・義務を、相続人が引き継ぐことです。相続の具体的な仕組みは民法などで規定されていますが、相続人同士で揉め事になることも少...
遺留分とは相続人が最低限の遺産を確保するための制度です。侵害された場合には遺留分侵害額請求により財産を取り戻すこともできます。ただし、この権利は被相続人の兄弟姉...
税理士費用とは、税理士に仕事を依頼する際に支払う料金のことで、税理士報酬や顧問料などが含まれます。この記事では、税理士費用の相場や内訳について解説します。
本記事では、相続手続きの流れや手順を解説します。また、各相続手続きの期限や手続きの仕方もあわせて紹介します。
本記事では、株式の相続での基本的な手続きの流れや評価方法・注意すべきポイントについて解説します。大切な財産を正しく引き継ぐために、株式相続の基本をしっかり押さえ...
相続時に被相続人の残高を確認できる残高証明書の取得方法を解説します。「ゆうちょ銀行」「三菱UFJ銀行」など、必要書類や手続きは銀行によってそれぞれ異なりますので...
所有物件・賃貸物件に関わらず、離婚・相続等により家の名義人が変わった場合には、名義変更をする必要が出てくるため、所有物件・賃貸物件それぞれの名義変更手続きを押さ...
記事では、2018年に成立した相続法の変更点を中心に、それぞれの制度を利用する際のポイントを解説します。また、自筆証書遺言の保管制度、相続時精算課税制度の見直し...
本記事では、外貨預金を相続するときの基本的な流れ、外貨預金と相続税申告の関係、外貨預金を相続するときに弁護士に相談するメリットなどについてわかりやすく解説します...
相続不動産の売却は3年以内が節税のカギです。「3000万円控除」と「取得費加算」、2つの特例を賢く使えば税金を大幅に減らせます。どちらがお得か、併用は可能か、と...
農地の相続は規制が多く、手続きも複雑です。相続した農地を売却するか、貸し出すか、農業を続けるか、それとも相続を放棄するかによって必要な手続きや負担が変わり、それ...
電話加入権は相続財産に該当します。そのため被相続人の死亡後もそのまま放置せず、相続人全員で話し合いNTTで必要な手続きをおこなう点に注意しましょう。本記事では、...
この記事では、相続における死亡届の役割や手続きの流れ、相続発生時に弁護士に相談するメリットなどについて解説します。悩みを抱えている方は、ぜひ参考にしてください。
相続の際、実印を押さない相続人がいると手続きが停滞し、相続財産を取得・活用できなくなります。また、相続人が増えて問題が長期化することもあるため、早期に対処するこ...
異母兄弟に相続の連絡をするときの流れや注意点、手紙を送るときのポイント、弁護士に相談・依頼するメリットなどについてわかりやすく解説します。
遺産確認訴訟は、特定の財産が相続財産に含まれるかどうかを裁判で確定する手続きです。ほかの手続きではトラブルを解決できそうにないケースや、遺産が高額なケースに有効...
将来の相続に備える「相続対策」には、大きく分けて3種類あります。家族の争いを防ぐ「遺産分割対策」、税金の負担を軽くする「相続税対策」、認知症などに備える「財産管...
相続不動産を売却した際、譲渡所得がマイナスなら確定申告は不要です。ただし譲渡所得の特例を利用する際や損益通算をおこなうときは、確定申告が必要になるため注意が必要...