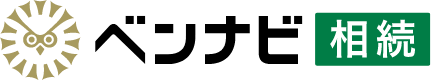相続放棄手続きの流れを6ステップで解説!弁護士に相談・依頼すべきケースも紹介

- 相続放棄で必要な手続きは何?
- 相続放棄の手続きって自分でできるの?
- 相続放棄にかかる期間を知りたい
- 相続放棄の3ヵ月の期限が過ぎそうだけど対処法はある? など
相続放棄手続きをおこなう場合、さまざまな疑問や不安があるでしょう。
本記事では、相続放棄の手続きが不安な方のために、手続きの流れや注意点を紹介します。
弁護士への相談・依頼をおすすめするケースも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
相続放棄の手続きとは遺産の全てを放棄すること

相続放棄手続きとは、相続権を持つ法定相続人が、被相続人の残した財産の一切の相続を拒否することです。
「一切の相続を拒否する」ということは、相続財産にあるプラスの財産(現金や不動産)とマイナスの財産(借金など)の両方を一切受け取らないということを意味します。
そして、相続放棄をおこなった相続人は最初から相続人ではなかったとみなされます。
相続放棄の手続きには期限がある
相続放棄手続きには期間期限が設けられています。
相続放棄の期限は「被相続人が亡くなったことを知ったときから3ヵ月」です。
相続放棄をおこなうには、この3ヵ月が経過する前に裁判所への申述書の提出を、おこなわなければなりません。
期限を過ぎると、単純承認として全ての遺産を通常どおり相続しなければならないため注意しましょう。
相続放棄の手続きを検討すべきケース
相続放棄の手続きは、以下のようなケースで検討しましょう。
- プラスの遺産よりも、マイナスの遺産のほうが多いとき
- 相続についてほかの相続人とトラブルになりたくないとき
相続放棄は一般的に、プラスの相続財産よりもマイナスの相続財産のほうが多いことがはっきりしており、相続人が借金などの不利益を被ることが明らかな場合に検討します。
また「相続争いに関わりたくない」「トラブルになるくらいなら遺産はいらない」という場合などについても、相続放棄を検討するのがよいでしょう。
なお、相続放棄の手続きをすべきかどうかは上記のケースに当てはまるかどうかに関わらず、一概に決めることはできません。
相続放棄をすべきかどうかで悩んでいたり、手続きを自分でできるか心配な場合は弁護士なへ相談するのがおすすめです。
相続放棄の手続きを弁護士に依頼すべきケース
相続放棄を自分でおこなうにはいくつかリスクがあるため、ケースによっては弁護士に依頼するのがおすすめです。
相続放棄の手続きを専門家に依頼すべきケースは、以下のとおりです。
- 遺産の種類が多く、相続財産の全体像がわかりづらい
- 相続放棄の期限までに手続きが間に合わない
- 相続人が多い、または疎遠な相続人がいる
- 遺産に不動産が含まれている
- 多忙・海外在住などの理由で手続きが難しい
- 確実に相続放棄をしたい
上記のケースに当てはまる場合は、相続放棄の手続きを自分でおこなわず、弁護士へまず相談することをおすすめします。
弁護士へ相談・依頼することでスムーズかつ確実に相続放棄手続きを進めることができるでしょう。
相続放棄の手続きを自分でおこなう流れ

ここでは、相続放棄手続きを自分でおこなう流れを解説します。
基本的な流れは以下のとおりです。
- 相続財産調査をおこなう
- 相続放棄の手続きにかかる費用を準備する
- 相続放棄の手続きの必要書類を用意する
- 家庭裁判所に相続放棄を申し立てる
- 家庭裁判所から照会書が届く
- 相続放棄が許可されたら相続放棄申述受理通知書が届く
1.被相続人の財産調査をおこなう
相続放棄をすべきかどうかを検討するために、まずは被相続人の財産調査をおこないましょう。
相続放棄は一度おこなうと原則撤回ができません。
「相続放棄の手続き後に、実は借金などの負債を上回る預貯金があったことがわかった」など、損をしないためにも、必ず事前にプラスの遺産とマイナスの遺産がそれぞれどれくらいあるのかを確認しましょう。
なお、相続財産は「預貯金」と土地や建物などの「不動産」に大きく分けられます。
預貯金は預金通帳や金融機関からの郵送物などで確認し、不動産は固定資産税通知書や名寄帳などで確認できるでしょう。
預金通帳に定期的な支払いがないかよく確認しましょう。
2.相続放棄の手続きにかかる費用を準備する
次に、相続放棄の手続きにかかる費用を準備しましょう。
相続放棄の手続きを自分でおこなう場合にかかる費用は、3,000円~5,000円程度です。
主な内訳は、必要な書類の取り寄せ費用や手続きの際の郵送代・印紙代であり、手続き自体にはそこまで費用はかかりません。
| 相続放棄手続きでかかる費用 | |
|---|---|
| 相続放棄の申述書に添付する印紙代 | 800円分の収入印紙(申述人1人) |
| 連絡用の郵便切手 | 500円程度(家庭裁判所による) |
| 被相続人の住民票除票または戸籍附票 | 300円程度(市区町村による) |
| 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 | 750円 |
相続放棄の手続きを誰がおこなうかによって必要な書類の数が異なるので、費用に多少の違いがあることを覚えておきましょう。
3.相続放棄の手続きの必要書類を用意する
次に、相続放棄の申立てに必要な書類を用意します。
相続放棄の必要書類は誰が申し立てるかによって異なりますが、以下の書類については共通して必要になります。
- 相続財産調査をおこなう
- 相続放棄の手続きにかかる費用を準備する
- 相続放棄の手続きの必要書類を用意する
- 家庭裁判所に相続放棄を申し立てる
- 家庭裁判所から照会書が届く
- 相続放棄が許可されたら相続放棄申述受理通知書が届く
このほか、申述人によっては追加で書類が必要になるので注意しましょう。
4.家庭裁判所に相続放棄を申し立てる
相続放棄の費用・必要書類が揃ったら、家庭裁判所へ相続放棄を申し立てましょう。
相続放棄は相続人本人が申し立てるのが原則です。
相続人が未成年の場合は、親などの法定代理人が申し立てることになります。
相続放棄の申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所が管轄している地域は、裁判所のホームページで確認できます。事前にチェックしておきましょう。
なお、相続放棄の手続きはここまでの流れ(家庭裁判所への申述手続き)を3ヵ月以内におこなえば大丈夫です。
5.家庭裁判所から照会書が届く
家庭裁判所に相続放棄を申し立てると、約10日後に家庭裁判所から相続放棄に関する照会書が送付されます。
照会書には回答を記入する欄があるので、必要事項を記入して家庭裁判所へ再送しましょう。
照会書には、申述の内容が真意に基づいているかや、単純承認にあたる内容がないかなどの確認事項が記載されます。
なお、単純承認にあたるかどうかは申述人本人が明確に判断できない場合があるので要注意です。
相続放棄の手続き前に、遺産を使ってしまっていたり、処分したりしている場合には、単純承認にあたる可能性があるので、弁護士に相談しましょう。
6.相続放棄が許可されたら相続放棄申述受理通知書が届く
照会書を再送してから10日ほどで、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送付されます。
相続放棄申述受理通知書の受取をもって、相続放棄が正式に認められたことになります。
相続放棄申述受理通知書は一度紛失すると再発行することができません。
相続放棄申述受理通知書がそのほかの手続きで必要になることはありませんが、念のため紛失しないように保管しておきましょう。
なお、相続放棄申述受理通知書に似た書類として、相続放棄申述受理証明書が存在します。
相続放棄申述受理証明書は相続放棄をした方が申請することで発行されます。
債権者からの支払い請求があった際に提示したり、金融機関での手続きに必要になったりするので、必要に応じて発行しておきましょう。
相続放棄の手続きを自分でする場合のリスクや注意点
相続放棄の手続きを自分でおこなう場合は、以下のようなリスクや注意点があります。
- 手続きが間に合わず期限が過ぎてしまう可能性がある
- 書類に不備があると裁判所から確認が入る可能性がある
- 相続放棄をすることで損をする可能性がある
- 別の相続人とトラブルになりやすい
- 相続放棄後の管理義務についてトラブルが起きる
- 照会書の書き方がわからず手続きが止まってしまう
- 内容によっては相続放棄の申請を却下されるリスクがある
それぞれのリスク・注意点について理解し、必要に応じて弁護士などの専門家に相談・依頼するようにしましょう。
1.手続きが間に合わず期限が過ぎてしまう可能性がある
相続放棄手続きを自分でおこなう場合、手続きの途中で何かしらのトラブルや不備があると期限を過ぎてしまう可能性があります。
特に、必要書類の収集には時間がかかりがちです。
相続放棄の必要書類は、申述人によって異なるので「取り寄せた書類が間違っていた」「追加で書類を取り寄せないといけなかった」などの理由で、期限内に書類を集められないケースもあります。
相続放棄の期限は思っていたよりも短く、期限を過ぎてしまうと単純承認として遺産を相続することになってしまうので、注意しましょう。
2.書類に不備があると裁判所から確認が入る可能性がある
相続放棄の申述をおこなったあとに書類の不備があると裁判所から呼び出される可能性があります。
相続放棄の手続きを自分でおこなう場合は、裁判所からの呼び出しにも自分で対応しなければならないので注意しましょう。
なお、弁護士などの専門家に手続きを依頼している場合は、裁判所からの連絡や呼び出しにも代理人として対応してもらえます。
3.相続放棄をすることで損をする可能性がある
相続放棄を自分でおこなう場合、相続放棄をすべきかどうかを正確に判断できない点もリスクとなります。
たとえば、相続放棄よりも限定承認のほうが適しているにも関わらず、自分の判断で相続放棄をしてしまったとしましょう。
その場合、本来受け取れるはずだった遺産まで放棄してしまい、損をすることになります。
ほかにも、相続財産調査の段階で財産の洗い出しができておらず、あとになって遺産が見つかったという事態もあり得ます。
相続放棄の手続きはもちろんですが、相続放棄をすべきかどうかを自分で判断する場合はリスクが伴うことを覚えておいてください。
4.別の相続人とトラブルになりやすい
相続放棄をおこなうと相続順位が自分の次の相続人に相続権が引き継がれます。
仮にマイナスの遺産が多い場合、自分が相続するはずだった分も次の相続人が負担することになってしまうため、あとになってトラブルに発展するケースもあります。
自分で相続放棄をおこなう際は、最低でも相続放棄をすることを次の相続人に伝えておきましょう。
また、弁護士などの専門家であれば、相続放棄をめぐってトラブルが発生しないように事前に対策をしてくれます。
トラブルを避けたい方は、専門家への相談も検討してみてください。
5.相続放棄後の管理義務についてトラブルが起きる
相続放棄をおこなっても、現状財産を占有している場合は相続財産清算人に財産を引き渡すまで管理義務を負うことになります。
相続放棄をおこなえば自分で管理する必要はないと勘違いしてしまいがちですが、管理を怠ったことでトラブルに発展する可能性があるので注意しましょう。
特に、被相続人と同棲していた場合や、名義が被相続人のままの車両を普段から使っている場合などは、管理義務が発生するので注意してください。
6.照会書の書き方がわからず手続きが止まってしまう
相続放棄の申述をおこなうと、裁判所から照会書が届きます。
照会書は必要項目を記載・回答して返送する必要がありますが、回答内容はケースによって異なります。
部分的に法律観点での判断が必要になるケースもあり、素人では何を書いたらいいかわからないこともあるでしょう。
照会書が届いた段階では相続放棄が正式に受理されたわけではないので、返送ができないと手続きがストップしてしまいます。
照会書の回答で悩んだ場合は、弁護士などに相談することも検討しましょう。
7.内容によっては相続放棄の申請を却下されるリスクがある
相続放棄は、申立てをすれば必ず受理されるわけではありません。
単純承認に当てはまっている場合はもちろん、そのほかの理由で却下される可能性もあります。
相続放棄の申請を一度却下されたあと、再申請で受理されるためにはそれなりの理由が必要になるため、却下されることは避けたいところです。
弁護士は相続放棄が受理されそうかどうかも判断できるので、事情があって相続放棄が受理されるか不安な場合は、事前に相談しておくとよいでしょう。
さいごに|相続放棄手続きで困っているなら弁護士へ相談を
相続放棄をするかどうか判断する際は、「プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのか」がポイントとなります。
しかし、判断にあたっては不動産の評価や相続財産調査などである程度の時間がかかる場合があります。
相続放棄の申立てには3ヵ月という期限があるため、相続が開始したら速やかにとりかからなければいけません。
自力で対応するのが不安な方は、相続放棄に注力している弁護士にサポートしてもらうことをおすすめします。
法律事務所によっては無料相談が可能なところもあるので、弁護士に依頼するべきかどうか悩んでいる方は、まずは一度話を聞いてみましょう。